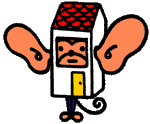【32】震度5弱。その時、工事現場は

▲前面道路から見た工事現場の全景。
2階の床が出来上がりつつある
■ここが一番、安全
3月11日、岡さんは手伝いに来ていた学生といっしょに、
蟻鱒鳶ルの現場で作業をしていました。
最初の大きな揺れが来た時は、
ちょうど休憩中だったといいます。
隣のマンションからは、
ガシャガシャーンと何かが壊れる音が聞こえてきます。
近くで工事中の高層ビルでは
2基のクレーンがぶつかり合っていました。
この建物も、まるで嵐の中の舟のように、
グラングランと揺れました。
「それはもう怖かった。
学生が『岡さん、逃げましょう!』と叫んだけど、
『いや、ここが一番安全だから』と言い返して、
現場に居続けました」
強気なところを見せたものの、
心のなかでは不安もよぎりました。
建物が崩れることはないにせよ、
どこかにひびが入るのではないか。
特に1センチぐらいの幅で柱が接しているところは、
割れてもしかたがないでしょう。
壊れるのなら、どこがどう壊れるのか、
自分で確かめておきたい、
そんな気持ちで目を凝らしていました。
しかし、一本のひびも入りません。
現場に積んである材料が崩れることもありませんでした。
岡さんは「ホッとすると同時に、うれしかった」
と言います。

▲現場の奥にはねじれながら伸びる
2本の柱が交差している。
地震による被害が心配されたが壊れなかった
■伝統的な材料での建築復興を
地震の後、工事を手伝っている大勢の仲間が
被災地へボランティア活動のために出かけました。
岡さんも、1995年の阪神大震災のときは、
寝袋をもって神戸に行っています。
今回も被災地で何かやらないといけないのではないか。
ずいぶんと悩みましたが、結局は東京に留まって、
自分の現場で頑張ろうと決心しました。
しかし仕事をしながらも、
ついつい東北のことに思いがいってしまうといいます。
被災地をどのようにして復興していくべきなのか。
どんな建築をそこに建てていけばいいのか。
岡さんが考えるのは、
昔ながらの土と木といった
伝統的な材料だけで建築をつくったらいいのでは、
ということです。
そうすれば有害な化学物質に悩まされることなく
健康的な暮らしが送れるだけでなく、
仮に再び大津波が来て、建物が流されたときでも、
やっかいなガレキが最小限で済みます。
「でも現実的には、復興を早く進めたいという理由から、
従来通り新建材が使われてしまうのでしょうね。
これだけの震災があっても、
建築のあり方を変えるのは難しい」
■200年残る建築とは
今回の震災で明らかになったのは、
数百年に一度起こる災害というものに対して
建築がどう立ち向かうのか、
そのことがほとんど考えられないままに
建築がつくられてきたという事実でした。
岡さんは、蟻鱒鳶ルを
200年先まで残る建築として構想しました。
それは200年に一度、
来るか来ないかという大災害がやってきても、
それに耐える建物をつくるという覚悟でもあります。
岡さんがふと思い出したのは、
民間のコンクリート研究者がこの現場を訪れた時のこと。
使っている砂利の産地を聞かれたので答えたら、
そこの砂は日本で一番いい、と教えてくれました。
具体的にどういう点がいいのか、と聞き返すと、
「あそこの砂は放射線の遮蔽性能が
圧倒的にすぐれている」との返答。
「そんな性能、欲しくもないよ」
とその時は思った岡さんですが、
今となってはありがたいと
思うようになってしまいました。
「イヤハヤ、ひどい世界に突入したものです」

▲工事現場の2階に立つ岡さん
|