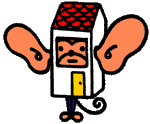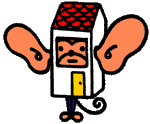【11】雨に降られても大丈夫。
久しぶりに現場を尋ねると、
雰囲気ががらりと変わっていました。
現場と道路の間にある柵が
青、黄、緑のペンキで塗られ、
「アリマストンビル現場」
「安全第一」
と掲げてあるのです。
すっかり華やかになった感じがします。

(クリックすると拡大します)
「子どもっぽく見えたらイヤだなと思ったんだけど、
手伝いに来たOくんが、
どうしても塗らせてくれというので‥‥」
と岡さんは消極的だった様子。
でも、結果的にはよかったようです。
「子どもを連れたお母さんから
『あら明るくなったじゃない』と言われました。
現場の前を通る人には好評のようです」
そのほかにも、現場にいると
いろいろな人が前を通っていきます。
たとえば日常的に現場の前を歩いていく
リハビリ中のお年寄りが3人います。
そのうち2人は以前から
にこやかに挨拶を交わしていましたが、
ひとりのおばあさんだけは
いつもむすっと黙ったままでした。
それが最近、
「がんばっていらっしゃいますね」
と声をかけてきてくれたのです。
これは岡さんもすごくうれしかったそうです。
自分の家づくりがまちの人に受け入れられるだろうか、
岡さんはずいぶんと心配していましたが、
今のところは、非常によい関係が成り立っているようです。
■梅雨をまたぐな、と言われたが‥‥。
さて、工事の進捗状況はというと、
地下の穴掘りが終わって、
これからコンクリートを打とうかという段階です。
実は当初の予定では6月の梅雨の前には
地下のコンクリートは打ち終わっているはずでした。
それは雨がたくさん降ると、
せっかく掘った穴が崩れてくるおそれがあるからです。
土木工事の専門家も、
「穴を掘ってからコンクリートを打つまで、
梅雨の時期をまたがないようにするべし」
とアドバイスしてくれていました。
それが穴を掘るまでに手間どり、
堀り終わるころにはもう6月という進行状況でした。
あわてて進めるのもよくないな、と判断した岡さんは、
コンクリートをすぐに打つことをあきらめ、
まず土の壁が崩れないようにするにはどうしたらいいか、
を考えることにしました。
最初は埋め戻した土を、
築地塀(*)をつくるときのように、
たたいて固くするという方法を試したそうです。
*築地塀(ついじべい):
土を厚く積んで上に瓦を載せた塀のこと。
でもこれはほんのちょっと工事するのに
半日以上かかってしまい、
とうてい全部はやりきれないことがわかりました。
途方にくれていたころ、ヒントをくれたのは
コンクリートの調合設計をしているXさんでした。
「土は掘る前が一番強いんですよ」
なるほど、そうか。掘った直後の土はまだ強い。
乾燥して、そこに雨が入るとボロっといく。
それがわかった岡さんは、
余分に掘って埋め戻すのではなく、
土をまっすぐ掘ることにし、
その土の面が乾燥して雨に打たれることがないように、
ラス網というネット状のものをかぶせて、
そのうえにモルタルを塗ったのです。
これはみんなに手伝いながらやってもらった
簡単な作業でしたが、効果は抜群で、
これで土の壁はガッチリともつようになりました。
雨に降られても大丈夫です。

(クリックすると拡大します)
■今はコンクリート工事の準備中
梅雨の時期が過ぎて、季節はとっくに秋ですが、
コンクリートを打つ工事はまだ始まっていません。
まだまだ準備や
検討しなければならないことがあるそうです。
「鉄筋を調達しなければいけないし、
型枠の材料も決めなくてはならないし‥‥」
そのほか、コンクリートを打つためには
工事現場に水道を引く必要もありますし、
砂や砂利を購入して現場に搬入するという作業もあります。
ミキサーの機械を狭い現場にどう入れるかも
悩ましいところです。
そうしたモロモロをクリアして、
工事はようやく次の段階に進むというわけです。
もうひとつ、夏の間、
工事があまり進んでいなかったのには理由があります。
岡さんは7月の終わりから8月の半ばにかけて、
岐阜県の山奥で行われる
建築のワークショップに出かけていたのでした。
高山建築学校というそのワークショップは、
岡さんが建築について大きな影響を受けた場です。
ですので次回は、
高山建築学校について簡単に触れておこうと思います。

(クリックすると拡大します)
写真=丸井隆人 |