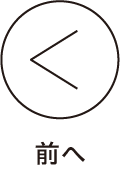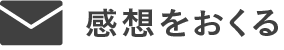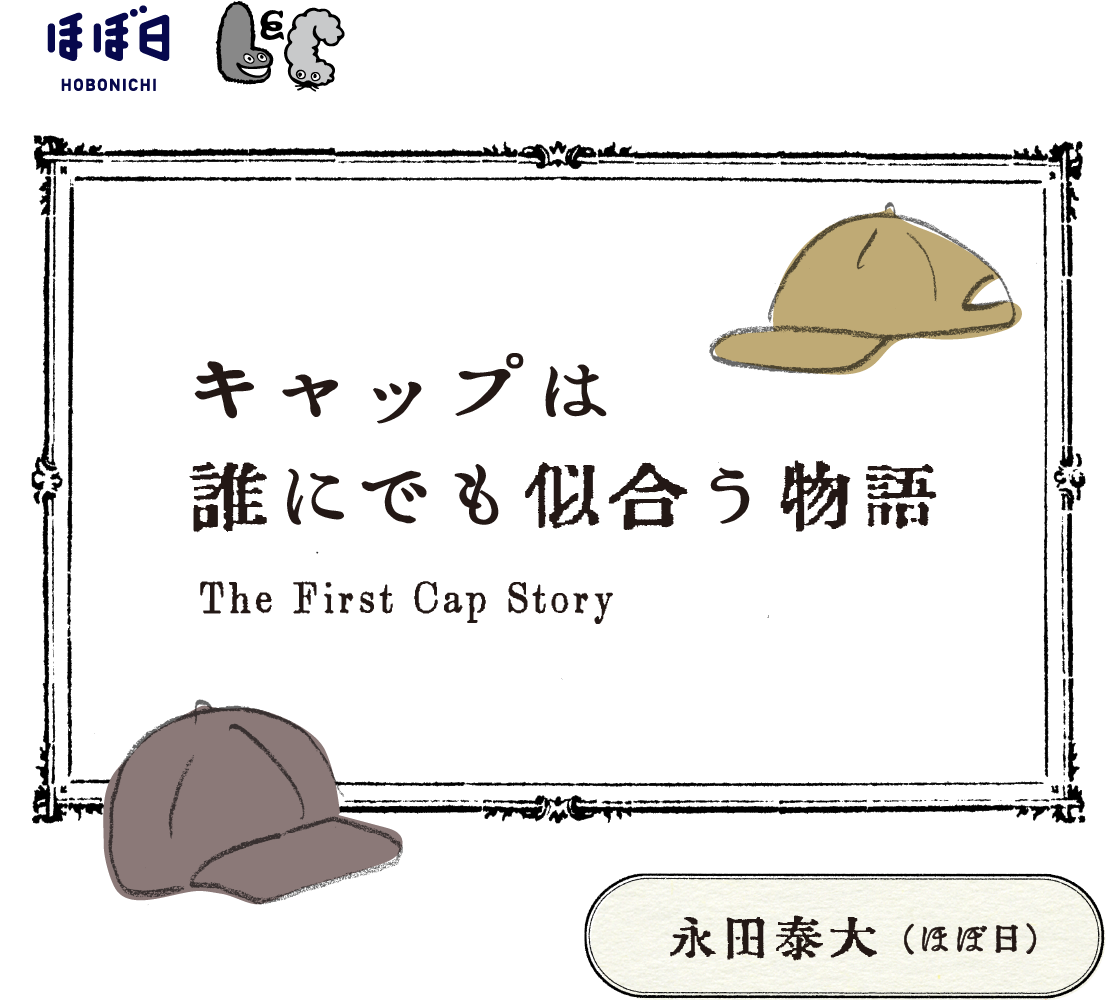
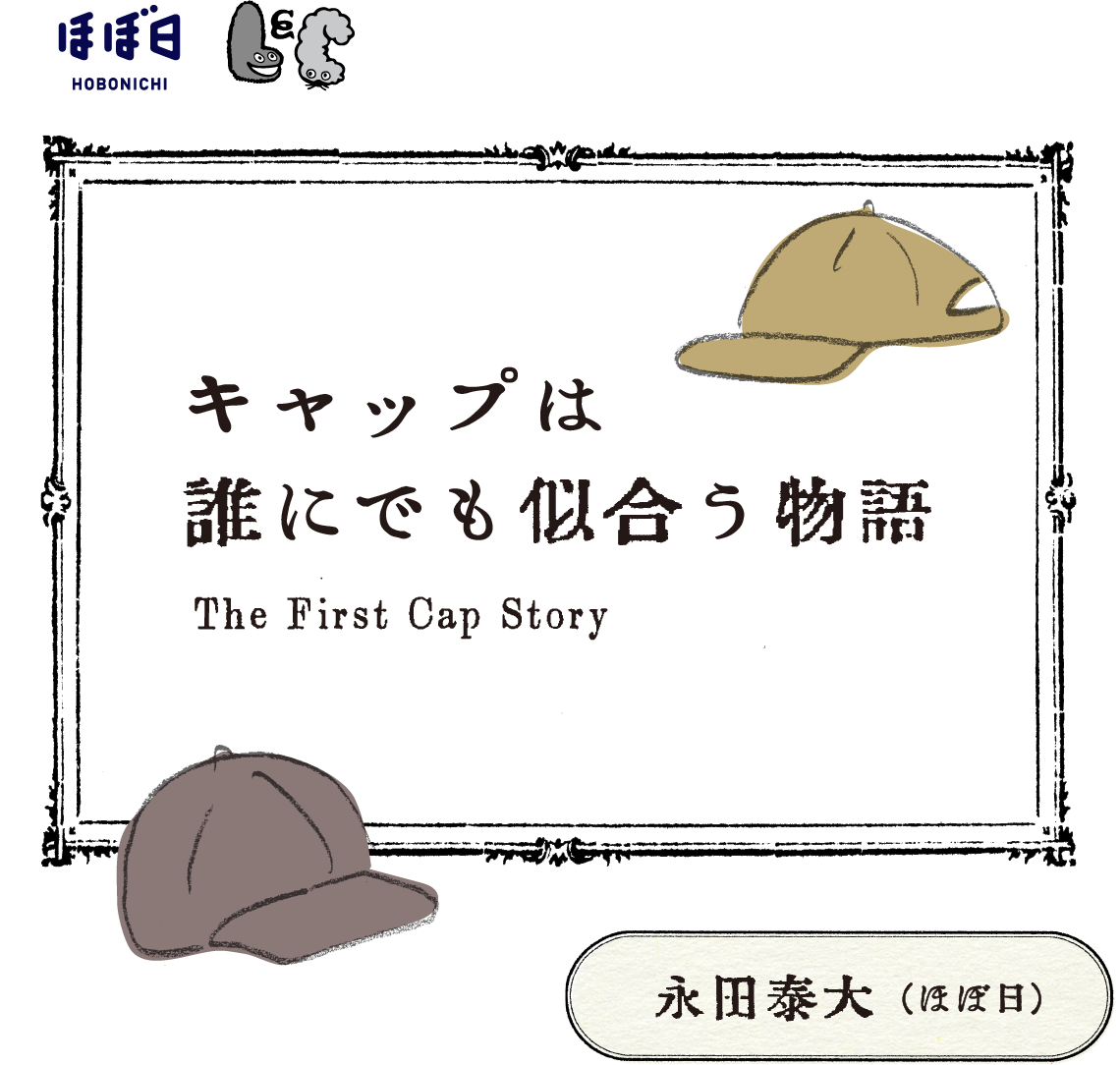
世の中には二種類の人間がいる。
帽子をしょっちゅうかぶる人と、
帽子をあんまりかぶらない人である。
あきらかに前者である書き手が、
後者の読み手へと理想のキャップを
紹介していく長く酔狂な物語。
しかし、その論はとても現実的で、
意外な展開で読み手を翻弄し、
現実的なデータに帰結するという。
さあ、はじまり、はじまり。
帽子をしょっちゅうかぶる人と、
帽子をあんまりかぶらない人である。
あきらかに前者である書き手が、
後者の読み手へと理想のキャップを
紹介していく長く酔狂な物語。
しかし、その論はとても現実的で、
意外な展開で読み手を翻弄し、
現実的なデータに帰結するという。
さあ、はじまり、はじまり。
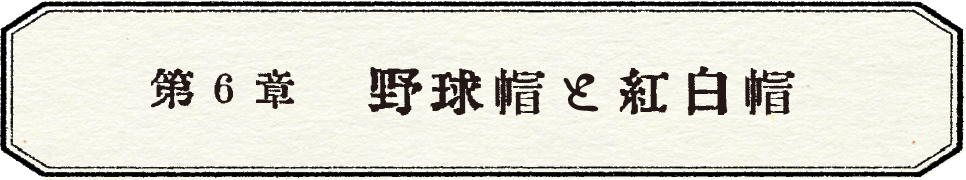
さて、みなさん。
これまでに色やツバなど、
キャップにまつわるさまざまな話をしてきましたが、
なんとなんと、重要なのはここからですよ。
そう、キャップの「本体」の話です。

つまりそれはかぶる人の頭をつつむ部分。
帽子のもっとも帽子たる部分。
専門用語でいうとクラウンと呼ばれるところ。
そこは、どういうかたちが望ましいのか。
いや、先に言っておくとね、
この部分はほんとうに
選択肢が無限なんです。
どこにどういう空間をつくるか、
理想的なフォルムはどうあるべきなのか、
それをどういうパーツで構成するのか‥‥。
ディテールを見つめていくとキリがない。
だから、もっとわかりやすい
大きな部分から話を進めていこう。
これまでに色やツバなど、
キャップにまつわるさまざまな話をしてきましたが、
なんとなんと、重要なのはここからですよ。
そう、キャップの「本体」の話です。

つまりそれはかぶる人の頭をつつむ部分。
帽子のもっとも帽子たる部分。
専門用語でいうとクラウンと呼ばれるところ。
そこは、どういうかたちが望ましいのか。
いや、先に言っておくとね、
この部分はほんとうに
選択肢が無限なんです。
どこにどういう空間をつくるか、
理想的なフォルムはどうあるべきなのか、
それをどういうパーツで構成するのか‥‥。
ディテールを見つめていくとキリがない。
だから、もっとわかりやすい
大きな部分から話を進めていこう。
まず、みなさんに
思い浮かべていただきたいのは「野球帽」だ。
まさに、高校球児がかぶっているようなキャップ。
思い浮かべましたか?
ああいう野球帽には、
おでこのところに硬い布が入っている。
だから、こう、正面の部分が、
すこし前に立つようになっている。
パッド、とはいわないけれど、
頭の形とは無関係に、硬い布の強度によって、
正面が立ち上がるようになっている。
おでこのところの布に芯がある、という感じ。
これを、野球帽タイプ、としましょう。
仮にね。

で、その真逆のタイプとして思い浮かべてほしいのは、
小学校の体育のときにかぶった「紅白帽」である。
あれって、硬い部分がなくて、
全体にくにゃくにゃでしょう?
だから、かぶると、帽子の布が、
頭のかたちにぴったり沿う感じになる。
わかりますよね?
これを、紅白帽タイプ、としましょう。
仮にね、あくまでも。

思い浮かべていただきたいのは「野球帽」だ。
まさに、高校球児がかぶっているようなキャップ。
思い浮かべましたか?
ああいう野球帽には、
おでこのところに硬い布が入っている。
だから、こう、正面の部分が、
すこし前に立つようになっている。
パッド、とはいわないけれど、
頭の形とは無関係に、硬い布の強度によって、
正面が立ち上がるようになっている。
おでこのところの布に芯がある、という感じ。
これを、野球帽タイプ、としましょう。
仮にね。

で、その真逆のタイプとして思い浮かべてほしいのは、
小学校の体育のときにかぶった「紅白帽」である。
あれって、硬い部分がなくて、
全体にくにゃくにゃでしょう?
だから、かぶると、帽子の布が、
頭のかたちにぴったり沿う感じになる。
わかりますよね?
これを、紅白帽タイプ、としましょう。
仮にね、あくまでも。

すごく大きくいえば、
キャップのおでこのところに、
硬い芯のある布を入れるかどうか。
その選択ひとつで、
まずは大きくキャップの路線が決定する。
おでこの布に芯を入れると
そこに立体感が出る。
ふつうの布にすると頭の形に沿う。
むろん、それぞれに一長一短ある。
野球帽タイプは
キャップに自動的に高さが出る。
それが頭部のバランスを
補正することもある。
一方で、ボリュームが出すぎちゃうこともある。
頭のかたちがどうあれ、きれいな立体感が出る一方、
ちょっと、運動部っぽい感じになるかもしれない。
紅白帽タイプは、
もともと頭の形がいい人には、
きれいにフィットする。
たとえば、ほら、芸能人とかセレブのみなさんが、
お出かけのときなどにかぶっているのは、
だいたいこの芯のないタイプだと思う。
やわらかさや女性っぽさが出る一方で、
バランスや頭の形を補正してはくれない。
キャップのおでこのところに、
硬い芯のある布を入れるかどうか。
その選択ひとつで、
まずは大きくキャップの路線が決定する。
おでこの布に芯を入れると
そこに立体感が出る。
ふつうの布にすると頭の形に沿う。
むろん、それぞれに一長一短ある。
野球帽タイプは
キャップに自動的に高さが出る。
それが頭部のバランスを
補正することもある。
一方で、ボリュームが出すぎちゃうこともある。
頭のかたちがどうあれ、きれいな立体感が出る一方、
ちょっと、運動部っぽい感じになるかもしれない。
紅白帽タイプは、
もともと頭の形がいい人には、
きれいにフィットする。
たとえば、ほら、芸能人とかセレブのみなさんが、
お出かけのときなどにかぶっているのは、
だいたいこの芯のないタイプだと思う。
やわらかさや女性っぽさが出る一方で、
バランスや頭の形を補正してはくれない。
さあ、どうする。
キャップづくりにおいて、
きわめて重要な二択。
我々は、大いに悩んだ‥‥かというと、
じつは、そんなに悩まなかった!
なぜか。
最初のほうで書いたように、
帽子をよくかぶる人たちは、
あちこちで帽子をかぶっている。
帽子というのは千差万別で、
自分にぴたっとくるものに出会うのは、
なかなか難しいと知っているからだ。
だから、あちこちで、残念な思いをしている。
「ああ、この色のままで、もうすこしこうなら」とか、
「このサイズ感のままでもうちょっとフォルムを」とか、
「ツバだけこれと入れ替えてくれればいいのに」とか、
そういった、ここがこうならいいのになぁ、という、
惜しい思いをたびたび経験しているのだ。
キャップづくりにおいて、
きわめて重要な二択。
我々は、大いに悩んだ‥‥かというと、
じつは、そんなに悩まなかった!
なぜか。
最初のほうで書いたように、
帽子をよくかぶる人たちは、
あちこちで帽子をかぶっている。
帽子というのは千差万別で、
自分にぴたっとくるものに出会うのは、
なかなか難しいと知っているからだ。
だから、あちこちで、残念な思いをしている。
「ああ、この色のままで、もうすこしこうなら」とか、
「このサイズ感のままでもうちょっとフォルムを」とか、
「ツバだけこれと入れ替えてくれればいいのに」とか、
そういった、ここがこうならいいのになぁ、という、
惜しい思いをたびたび経験しているのだ。
というかね、例え話をするけどね、
世の中のお店に並んでる帽子って言ってみれば、
「辛さの調整ができないカレー」みたいなもんなんですよ。
あるカレー屋さんに入ってメニューを広げてみると、
「ビーフカレー激辛」と「キーマカレー甘口」と
「野菜カレー中辛」と「カツカレー辛さふつう」があって、
それぞれに辛さが固定されてて選べない、みたいな感じ。

そうじゃなくて、ひとつのメニューで
辛さを調整したいじゃないですか。
チキンカレーを選んだうえで、
今日は中辛かな、いや2辛かな、いっそ7辛、とか、
好みに近づけて注文したいじゃないですか。
ていうか、そうあるべきでしょう?
そこで、この似合うキャップをつくるプロジェクトは、
はじまりのところから、
そこをコンセプトにしていたのです。
すなわち、キャップのフォーマットをある程度定めて、
そのうえでバリエーションをもたせる。
すなわち、こういうことです。



それぞれのフォルムの差は、
写真だとわかりづらいかもしれません。
それくらい微妙な差を大事にしたのです。
かぶると、違いがしっかりわかります。
その微妙、かつ大切な、
3つのフォルムの違いについて説明しましょう。
世の中のお店に並んでる帽子って言ってみれば、
「辛さの調整ができないカレー」みたいなもんなんですよ。
あるカレー屋さんに入ってメニューを広げてみると、
「ビーフカレー激辛」と「キーマカレー甘口」と
「野菜カレー中辛」と「カツカレー辛さふつう」があって、
それぞれに辛さが固定されてて選べない、みたいな感じ。

そうじゃなくて、ひとつのメニューで
辛さを調整したいじゃないですか。
チキンカレーを選んだうえで、
今日は中辛かな、いや2辛かな、いっそ7辛、とか、
好みに近づけて注文したいじゃないですか。
ていうか、そうあるべきでしょう?
そこで、この似合うキャップをつくるプロジェクトは、
はじまりのところから、
そこをコンセプトにしていたのです。
すなわち、キャップのフォーマットをある程度定めて、
そのうえでバリエーションをもたせる。
すなわち、こういうことです。



それぞれのフォルムの差は、
写真だとわかりづらいかもしれません。
それくらい微妙な差を大事にしたのです。
かぶると、違いがしっかりわかります。
その微妙、かつ大切な、
3つのフォルムの違いについて説明しましょう。
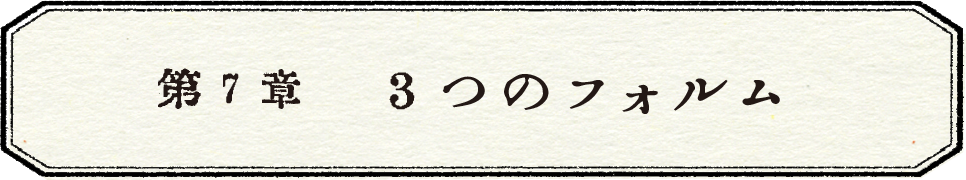
ようするに、我々が選択したのは、
色をキャメルとチャコールグレーの
2色に決めて、
ツバは自然にカーブしつつ幅を広めにし、
それを共通の要素としつつ、
キャップ本体のフォルムには
「複数のバリエーションをつくる」ことだった。
だって、何度も言うように、
頭のかたちは人によっていろいろで、
ひとつのキャップのフォルムが
万人に似合うということはないのだから。
色をキャメルとチャコールグレーの
2色に決めて、
ツバは自然にカーブしつつ幅を広めにし、
それを共通の要素としつつ、
キャップ本体のフォルムには
「複数のバリエーションをつくる」ことだった。
だって、何度も言うように、
頭のかたちは人によっていろいろで、
ひとつのキャップのフォルムが
万人に似合うということはないのだから。
さあ、しかし、簡単ではないよ。
バリエーションをもたせるといっても何種類にするか、
そして、それぞれをどんなフォルムにするか。
これはもう、理屈ではなく、ある意味、人力でした。
さまざまなサンプルを取り寄せて並べ、
かぶっては話し、いろんな人の声を聞き、
工場の人の意見なども聞きながら絞り込んでいった。
結果的に、バリエーションの数は3つに絞り込まれた。
それぞれのフォルムを説明していこう。
まずは、上で述べた、
「野球帽タイプ」と「紅白帽タイプ」という
両極端なタイプをかたちにしようということになった。
かといって、ガチで野球帽な感じとか、
モロに紅白帽フォルムのキャップをつくったわけではない。
ひとつひとつ、
こうあるべきという姿を追求した。
バリエーションをもたせるといっても何種類にするか、
そして、それぞれをどんなフォルムにするか。
これはもう、理屈ではなく、ある意味、人力でした。
さまざまなサンプルを取り寄せて並べ、
かぶっては話し、いろんな人の声を聞き、
工場の人の意見なども聞きながら絞り込んでいった。
結果的に、バリエーションの数は3つに絞り込まれた。
それぞれのフォルムを説明していこう。
まずは、上で述べた、
「野球帽タイプ」と「紅白帽タイプ」という
両極端なタイプをかたちにしようということになった。
かといって、ガチで野球帽な感じとか、
モロに紅白帽フォルムのキャップをつくったわけではない。
ひとつひとつ、
こうあるべきという姿を追求した。
まず野球帽タイプ‥‥
いや、正面に芯のあるタイプ。
ある意味、もっともキャップらしいキャップだ。
頭部のかたちやフォルムを補正してくれるのはいいけれど、
あまりに運動部っぽい感じが出ないようにしたい。
具体的にいうと、正面の硬い布は、
壁みたいに真っ直ぐ立ち上がるのではなく、
そこそこの角度で、しかも、立ち上がった部分に、
それほど高さが出ないように。
いってみれば、横から見たとき、
おでこのあたりに自然なカーブがかぶさってる感じで。
かたちとしては、
キャップらしい「スタンダード」なタイプ。
しかし、オリジナリティも「プラス」して。
そういう意味で、このタイプには
「STANDARD PLUS
(スタンダードプラス)」
という名前をつけました。

いや、正面に芯のあるタイプ。
ある意味、もっともキャップらしいキャップだ。
頭部のかたちやフォルムを補正してくれるのはいいけれど、
あまりに運動部っぽい感じが出ないようにしたい。
具体的にいうと、正面の硬い布は、
壁みたいに真っ直ぐ立ち上がるのではなく、
そこそこの角度で、しかも、立ち上がった部分に、
それほど高さが出ないように。
いってみれば、横から見たとき、
おでこのあたりに自然なカーブがかぶさってる感じで。
かたちとしては、
キャップらしい「スタンダード」なタイプ。
しかし、オリジナリティも「プラス」して。
そういう意味で、このタイプには
「STANDARD PLUS
(スタンダードプラス)」
という名前をつけました。

そして、紅白帽タイプ‥‥
というか、布に芯のないタイプ。
運動部っぽさを感じさせず、
出かけるときに選ぶ服の延長にあるような、
カジュアルっぽさと落ち着きのあるたたずまい。
自然に頭のカーブに沿って、
あまり大げさな補正をせず、
纏うようにかぶれるキャップになればいいな、
と思いながらフィックスさせた。
頭のかたちに沿う「タイト」なタイプだから、
そのまま「TIGHT(タイト)」という名前にした。
こんな感じのキャップです。

というか、布に芯のないタイプ。
運動部っぽさを感じさせず、
出かけるときに選ぶ服の延長にあるような、
カジュアルっぽさと落ち着きのあるたたずまい。
自然に頭のカーブに沿って、
あまり大げさな補正をせず、
纏うようにかぶれるキャップになればいいな、
と思いながらフィックスさせた。
頭のかたちに沿う「タイト」なタイプだから、
そのまま「TIGHT(タイト)」という名前にした。
こんな感じのキャップです。

「スタンダードプラス」と「タイト」という
ふたつのフォルムが決まったとき、
この2種類だけでいいんじゃないかとも思った。
このふたつのフォルムがあれば、
きっとかなり多くの人の望むキャップをフォローできる。
けれども、ひとつ、解決したいポイントがあった。
具体的には、「タイト」を軸にしたものです。
頭のかたちとしては、「タイト」を選びたいんだけど、
「タイト」をかぶったときに、
頭の上に帽子がちょこんと乗っかった感じになってしまう。
とくに、眉毛あたりからつむじまでの高さがある人は、
そういう傾向があることがわかった。
つまり、そういう人にとって、「浅い」のだ。
そういえば、世の中には「タイト」タイプの
キャップはけっこうあるけど、
ほとんどが「浅い」タイプだ。
基本のかたちは「タイト」でありながら、
もうすこし「深く」かぶれるキャップ。
それって、世の中には、なかなかない。
だったら、つくる意味があるんじゃないか。
「タイト」だけど、すこし「深く」かぶれるキャップ。
名前は「TIGHT DEEP(タイトディープ)」に
しました。
じつは、「タイト」と「タイトディープ」の差は、
ほんのちょっとです。もう、数センチくらい。
でも、かぶってみると、違う。
キャップにかぎらず帽子って、
その数センチがすごく違うんですよね。
「タイトディープ」はこんな感じです。
写真だとあまり違いがわからないかもしれないけど、
かぶると、その「深さ」を実感できると思います。

ふたつのフォルムが決まったとき、
この2種類だけでいいんじゃないかとも思った。
このふたつのフォルムがあれば、
きっとかなり多くの人の望むキャップをフォローできる。
けれども、ひとつ、解決したいポイントがあった。
具体的には、「タイト」を軸にしたものです。
頭のかたちとしては、「タイト」を選びたいんだけど、
「タイト」をかぶったときに、
頭の上に帽子がちょこんと乗っかった感じになってしまう。
とくに、眉毛あたりからつむじまでの高さがある人は、
そういう傾向があることがわかった。
つまり、そういう人にとって、「浅い」のだ。
そういえば、世の中には「タイト」タイプの
キャップはけっこうあるけど、
ほとんどが「浅い」タイプだ。
基本のかたちは「タイト」でありながら、
もうすこし「深く」かぶれるキャップ。
それって、世の中には、なかなかない。
だったら、つくる意味があるんじゃないか。
「タイト」だけど、すこし「深く」かぶれるキャップ。
名前は「TIGHT DEEP(タイトディープ)」に
しました。
じつは、「タイト」と「タイトディープ」の差は、
ほんのちょっとです。もう、数センチくらい。
でも、かぶってみると、違う。
キャップにかぎらず帽子って、
その数センチがすごく違うんですよね。
「タイトディープ」はこんな感じです。
写真だとあまり違いがわからないかもしれないけど、
かぶると、その「深さ」を実感できると思います。

そんなわけで、2色✕3タイプ、
ぜんぶで6つのバリエーションが完成しました。
それぞれのタイプはすべて後ろにアジャスターがあって、
頭囲に合わせてサイズは調整することができます。
これら全体のキャップのシリーズ名は、
ふだんはキャップをかぶらない人にもかぶってほしい、
はじめてのキャップにしてほしい、という意味をこめて、
「ファースト・キャップ」という名前にしました。
ぜんぶで6つのバリエーションが完成しました。
それぞれのタイプはすべて後ろにアジャスターがあって、
頭囲に合わせてサイズは調整することができます。
これら全体のキャップのシリーズ名は、
ふだんはキャップをかぶらない人にもかぶってほしい、
はじめてのキャップにしてほしい、という意味をこめて、
「ファースト・キャップ」という名前にしました。
ずいぶん長く紹介してきましたが、
いよいよ、これで、すべてお伝えした、でしょうか?
いえ、ごめん、まだあります。
ほぼ日では、なにかをつくっていて、
「だいたいできたけれど、なにかひとつ、
はっとするような魅力が足りない」というとき、
「イチゴが足りない」という言い方をします。
これは糸井重里がよくつかうたとえで、
いくらショートケーキのスポンジとクリームを
上手においしくつくったところで、
その上にイチゴがないと人はよろこばないんだよ、
ということです。

色を選び、ツバを選び、フォルムを3つに決めて、
ファーストキャップはとてもよくできたと思います。
でも、そこに、ぜひ、「イチゴ」を乗っけたい。
いよいよ、これで、すべてお伝えした、でしょうか?
いえ、ごめん、まだあります。
ほぼ日では、なにかをつくっていて、
「だいたいできたけれど、なにかひとつ、
はっとするような魅力が足りない」というとき、
「イチゴが足りない」という言い方をします。
これは糸井重里がよくつかうたとえで、
いくらショートケーキのスポンジとクリームを
上手においしくつくったところで、
その上にイチゴがないと人はよろこばないんだよ、
ということです。

色を選び、ツバを選び、フォルムを3つに決めて、
ファーストキャップはとてもよくできたと思います。
でも、そこに、ぜひ、「イチゴ」を乗っけたい。
写真を見てもらえればわかるように、
ファーストキャップは「無地」です。
チーム名とかブランド名はそこに入りません。
多くの人に、広く受け入れてもらうことが、
このキャップの根底にあるコンセプトですから、
それは最初から決めていたことです。
しかし、まったく完全にのっぺらぼうというのも、
なんだかちょっとさびしくないですか?
そこで、私たちは、このキャップに、
すばらしい「ワンポイント」を加えてくださるであろう、
アーティストのかたにオファーをしました。
間違いなく忙しい方なので、
なかなかむずかしいだろうと思っていたのですが、
なんと、引き受けていただき、
すてきな「イチゴ」を描いてくださいました。
その方は、ヒグチユウコさんです。
ファーストキャップは「無地」です。
チーム名とかブランド名はそこに入りません。
多くの人に、広く受け入れてもらうことが、
このキャップの根底にあるコンセプトですから、
それは最初から決めていたことです。
しかし、まったく完全にのっぺらぼうというのも、
なんだかちょっとさびしくないですか?
そこで、私たちは、このキャップに、
すばらしい「ワンポイント」を加えてくださるであろう、
アーティストのかたにオファーをしました。
間違いなく忙しい方なので、
なかなかむずかしいだろうと思っていたのですが、
なんと、引き受けていただき、
すてきな「イチゴ」を描いてくださいました。
その方は、ヒグチユウコさんです。
(わくわくしながらつづきます)
2025-05-12-MON