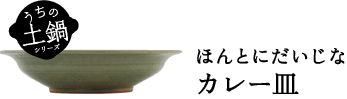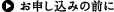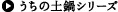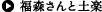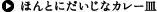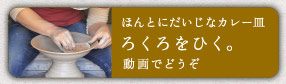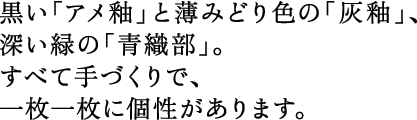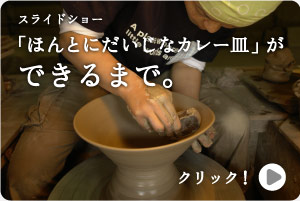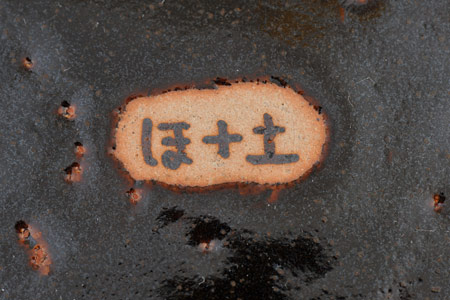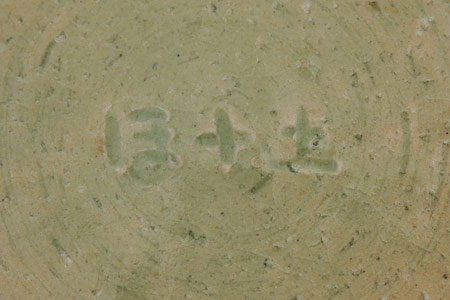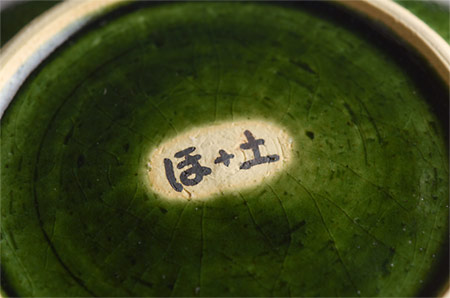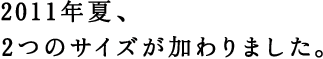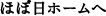「ほんとにだいじなカレー皿」は、
糸井重里のひと言からはじまりました。
「カレーを食べるとき、
ほんとに食べやすいお皿って、
なかなか、ないんだよ」
手にしっくり収まって片手で持てること。
ごはんの最後のひとつぶまで
スプーンで気持ちよくすくうことができること。
そして、カレーはもちろん、
いろいろな家庭料理に映えること。
そんなカレー皿がほしい、
という「ほぼ日」のリクエストに、
1年かけて実際のかたちにしてくれたのが
「土楽」の四女で、陶芸家の福森道歩さんでした。 |
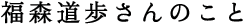

福森道歩さんは、
ほぼ日乗組員が「土楽」を訪れるときは、
いつも屈託のない元気な笑顔で出迎えてくれます。
気さくで気取っていない人柄なので、
彼女に会う、ほぼ日乗組員、
みんな揃ってファンになってしまう、
そんな親しみやすくフレンドリーな人なのです。
ところが、
ひとたび、轆轤の前に座ると、
その表情はガラリと真剣なものになります。
両の手にひねられる器を見つめる彼女の眼差しの
鋭さと美しさは、言葉ではいい表せないものです。
四季折々の伊賀の自然、
父の器、新鮮な食材、舌鼓を打つ料理、
生まれてからずっと土楽窯に育った道歩さんは、
そのどれもをごく当たり前のものとして、
日常のなかで触れてきました。
そんな生粋の土楽育ちの彼女の感性から
生み出される器は、やはり素晴らしいものです。
日々愛用され、空気のようにそこにあり、
前に出ず後ろに下がらず
料理を引き立てる。
そして、時の経過とともに、
変わりゆく表情を楽しませてくれる。
道歩さんの手からひねり出されるのは、
やはり土楽ならではの器なのです。
土楽窯7代目当主であり、
父でもある、福森雅武さんもが認める
福森道歩。
「ほんとにだいじなカレー皿」は、
そんな彼女が
1年間という長い時間をかけて開発し、
丹精を込めて手づくりする器なのです。 |
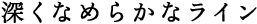
「ほんとにだいじなカレー皿」の
底から縁に向かって立ち上がるラインは、
スプーンをそえてカレーをすくうときに、
なめらかにすくいやすく、
カレーや、ごはんがこぼれにくいつくりになっています。

 |
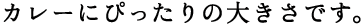
「ほんとにだいじなカレー皿」の大きさは
直径24.5センチ、高さ5センチとなっています。
ひとりぶんのカレーをよそったときに、
ちょうどいい大きさを考えました。
スープたっぷりのカレーでも、こぼれにくい深さ。
たくさん食べるかたが、大盛りにしても、
きゅうくつな感じにはならないよう、
じゅうぶんな容量をもっています。
 |
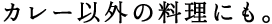
カレーを盛るためにつくったお皿ですが、
和洋中、さまざまな料理とも相性のよいお皿です。
ぜひ、毎日の食卓で、お使いいただけたらと思います。





 |
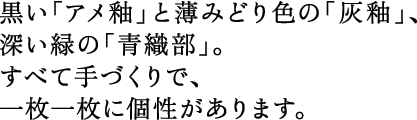
「ほんとにだいじなカレー皿」は、
福森道歩さんが、一枚一枚、
ろくろを回し、手づくりをしています。
色は3種類。
これは、かける釉薬の色のちがいによるものです。
「ベア1号」と同じ、黒と茶がまじった色は「アメ釉」、
薄緑色のほうは「灰釉」で仕上げています。
2016年夏に深緑色の「青織部」が加わりました。
土楽の職人さんが一枚ずつ、手作業で釉薬をかけ、
焼き上げていますので、
その色や光り方には、一枚一枚の個性があります。


 |
|
|
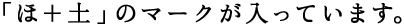
「ほんとにだいじなカレー皿」の裏側には
高台(こうだい)と呼ばれる
皿を安定させる台があり、その中央には
「ほ+土」の名前があります。
これも、一枚一枚手書きで入れています。
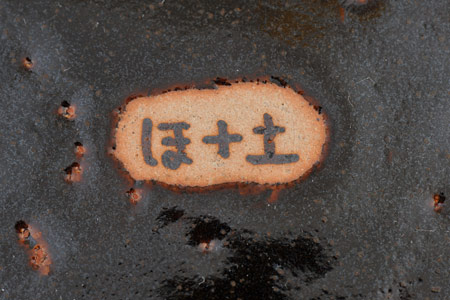
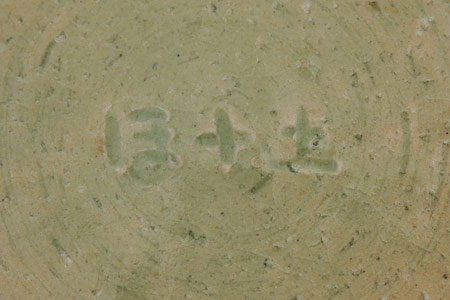
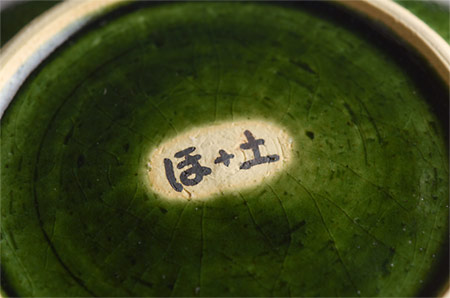
|
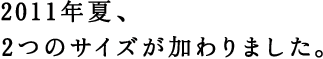
「ほんとにだいじなカレー皿」に加えて、
中ぐらいの「中(なか)のカレー皿」と
小さい「ひとくちカレー皿」がなかまに加わり、
ぜんぶで3サイズになりました。


 |