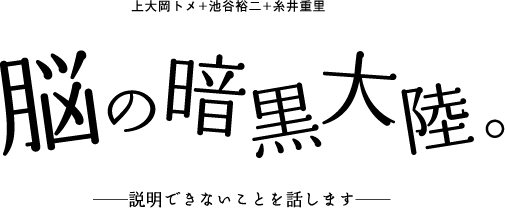| 糸井 |
僕はよく、組織のことを考えるときに、
からだのことを引き合いに出します。
小指をどこかにぶつけてしまったときって、
小指の先だけしか痛くないはずなのに、
全体の調子がすごく悪くなるでしょう? |
| 上大岡 |
そうですね。
ひとつ怪我しただけで、全体的な
体のバランスが崩れます。 |
| 糸井 |
そこをかばうために、
ほかがすごく疲れるからですよね。
組織でも同じことが言えて、
「俺はいいから」とがんばっている人が
ひとりいるだけで、
まわりはそれを無意識でかばってしまいます。 |
| 池谷 |
それを伺って、ふと思ったんですが、
いま、鍼が効くということについて、
メカニズムがずいぶんわかってきてるんです。 |
| 上大岡 |
それも、1か所の刺激で、
体全体が変わるということですよね。 |
| 池谷 |
ええ。鍼は、言ってしまえば
特定の部分に鍼を刺して
細胞を壊しているだけなんです。
そうするとその内容物が出てきて、
反応が起こるわけです。
皮膚は再生するから、刺しても大丈夫なんですが、
細胞が死ぬということは、
危険信号なんですよ。 |
| 上大岡 |
はい、はい。 |
| 池谷 |
刺した信号が
神経に作用し、全身を巡ります。
神経線維がいっぱい集まっているところが
いわゆるツボなんです。
だから、たった1か所の刺激なんだけど、
一見関係ないところが
治療できるみたいなんですよ。 |
| 糸井 |
今の説明はおもしろいですね。
うん、そのとおりですね。
おもしろいなぁ。
脳が、ほかの反射的な神経細胞に比べて、
ちょっと優位性があるように見えるのは、
蓄積したデータを
参照できるというところですよね。
「参照の側」に重きが置かれすぎだ、
ということがあるんじゃないかなぁ。 |
| 池谷 |
一応、皮膚も参照はするんですよ。
危険なことをしようとすると汗ばんでしまう、
というのは、
以前イヤな思いをしたということを覚えていて、
その記憶を参照しているからで。
だけど、糸井さんの言うように、
意識のほうが
だんぜん参照の度合いが強いです。 |
| 糸井 |
情報はいっぱいになっていくし、
これ以上、参照型の学問に
とらわれることはないと思うんですよ。
軽く動きのある学問、ってないのかなぁ。
そう言えば池谷さんは、
論文があまりにも発表されるから、
全部参照できないことがわかったんで、と
発表された論文を
パソコンのスクリーンセーバーに
なさってるんですよ。 |
| 上大岡 |
そうなんですか。 |
| 池谷 |
そうです。
いま、3画面で出してます。
ただ、スクリーンセーバーは
待たないと出ないですよね。
情報を得るまでに時間のロスが生じるので
最近は、1台のパソコンの
画面の下の部分に、常に流してます。 |
| 上大岡 |
電光掲示板状態ですね(笑)。 |
| 糸井 |
その電光掲示板で流れる論文に
出会えるか出会えないかはもう、
偶然ですよね。 |
| 池谷 |
偶然です。
だけど、不思議と、
科学的に推論を進めて論文を書くときに
参照するのは、なんだかんだいって、
結局、自分の好きな論文なんです。
これは「正しい」「間違っている」という
話になると、
もうひじょうに難しい話になっちゃうんですが‥‥
まず、前提として、
自分の好きな過去の論文というものは、
あるんです。
おもしろいもんですね、
電光掲示板状態のパソコンに
たくさんの情報が流れていると、
視野のところで気になる論文があったら
何をやってても気づくんですよ。
そして、気づく論文って、
あとからいろいろ考えてみると、
同じ著者であったり、
好きなタイプの研究なんです。 |
| 上大岡 |
呼ばれているんですよね。 |
| 池谷 |
そういうことですね。 |
| 上大岡 |
私は「なんとなく」っていう言葉が
すごく好きなんです。
理由はわかんないんだけど、
なんとなく気になって行ってみた、
なんとなく会ってみた、
そういうことって、後であたったり、
何かとつながったりするんです。
「なんとなく」はすごく重要な気がするんです。 |
| 糸井 |
ジャッジするときに、
「なんとなく」っていうような
感じがしちゃったら、
もう、ジャッジはできないですよね。 |
| 上大岡 |
うん。できません。 |
| 糸井 |
「リンゴ好きです」というときに
「どうして好きですか?」って
聞かれても、どうにもなんないですよね。
「栄養があるから」っていうのも違うし(笑)。 |
| 上大岡 |
言葉にはできない何か、
ホントに「なんとなく」としか言えない
何かなんですよ。 |
| 池谷 |
そうですね。
例えば、センスっていうのは
言葉にはならないといわれています。
芸術作品などもそうですが、
言葉にならないけど、
こっちのほうがいいとは、なぜか判断できる、
そういうことは、もうしょうがないわけです。
そういう感覚って、
かなり無意識のところから生まれています。
脳の部位でいうと
基底核(きていかく)とか小脳という場所です。
ここの活動は意識にのぼらないんです。
ほんとうはちゃんと論理的に
考えているんだろうけれども、
答えだけがわかる、というものを
出してくる場所なんです。
だから「こっちのほうがいい」という、
最終結果だけはわかるんだけど、
その途中どういう思考をたどっているか、
自分では言えないんですよ。
一方、大脳皮質はすごく意識的で、
「これこれこうなって、こうなって、
こうなって、だからこうでしょ」
というふうに、ちゃんと論理的に
口で説明できます。
このふたつが脳の中にあって、
おそらく二重構造をしているんです。
大脳皮質は、哺乳類で大きく発達しています。
だけど、基底核という、
言葉にならないけれども
答えだけわかっちゃうようなシステムって、
哺乳類以外の動物、例えば
鳥類や爬虫類や両生類、
それに魚類にまであるんですよ。 |
| 上大岡 |
へぇ、魚も? |
| 池谷 |
例えば自分が魚だったとしてください。
いま、大きな魚に追われていて
目の前に岩がある。
ふたつに分かれた流れの
どちらかへ逃げ込む場合、
瞬間的にどちらを選ぶかは、
魚はおそらく論理的思考では考えてなくて、
直感みたいなもので
「こっちだ」と逃げると思います。
でもたぶん、魚は
理にかなった判断を絶対に
しているはずなんですよ。
そうじゃないと、自然淘汰で生き残れませんから。
そういう、意識に残らないけど
理にかなった判断がちゃんとできる、
センス、つまり直感が働く動物が、
ずっと生き残ってきて、
人間までやって来たんです。
ですから、人間にはそういう
言葉に説明できないセンス、勘、
沈黙に含まれた何か、
言葉にならない何か、
それがあると思うんです。 |
| (つづきます) |
| 2009-04-08-WED |