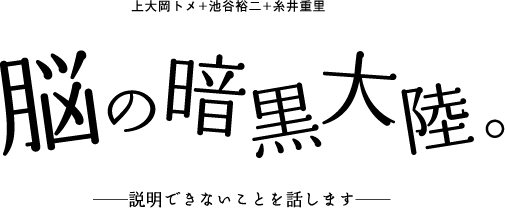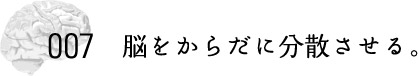|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 池谷 | 数年前、グランドキャニオン行ったとき、 ものすごーく、広大な景色が見えました。 向こう岸までは数十キロあって、 渓谷の左右は何百キロ見えてます、と 説明されたんです。 そう言われても、 自分のからだを超えすぎてしまっていて、 僕にはその距離が ぜんぜんわかりませんでした。 つまり、東京から名古屋くらいまでが、 今まさに、一気に見渡せているわけですが、 でも、そんなの実感がわかないんです。 われわれの目にわかる距離って、 せいぜい1キロとか、そのぐらいでしょう。 それを超えちゃったら、みんな同じ。 感覚的によくわからなくなってしまうのでは ないでしょうか。 人数も同じことで、 山岸先生がおっしゃった「150人」は、 ちょうどいい数字かもしれません。 |
 |
|
| 糸井 | 小さい単位で ものを考えていくことをしなかったら、 人間は地球上に 分布しなかったとさえ思います。 |
| 池谷 | ああ、なるほど、そうですね。 |
| 糸井 | 人間は、地球に 同心円的に拡大していったんじゃなくて、 分布していったわけですから。 そのたびに、 「俺、ここに残るわ」 というやつがいたんです。 しかも、ものすごい早さの 分布だったんですよね。 アフリカから出発して、アジア側に行った人、 インドネシアのほうに行った人、 ヨーロッパに行って、 シベリアから日本のほうに来た人、 アメリカに渡って、最後に チリの最先端で終わった。 「終わった‥‥」(笑) |
| 池谷 | しかも、移動する人数は、いつも少人数。 大移動じゃないんですよね。 ‥‥僕は、自分の研究で こだわっていることがありまして、 それについては世界最高記録を持っているんです。 |
| 上大岡 | 記録保持者? |
| 池谷 | そうなんです(笑)。 なんの記録かというと、 神経の活動をできるだけ高速に レーザー顕微鏡で画像化することです。 世界最高速の1秒間に2千枚です。 そして、高速というだけでなく、 僕がもうひとつこだわりたかったのは、 画像におさめるニューロンの数です。 だいたい数十個撮ると すごいと言われる業界ですが、 これまでの世界最高レベルは、1,000個でした。 僕も1,000個は撮ることができていましたから、 世界最高レベルです(笑)。 でも、それでは飽きたらず、 これを、もう1桁増やしたいと思いまして‥‥ |
| 上大岡 | できました? |
| 池谷 | はい、先月、10,000個を達成しました。 もうここまで行くと、 しばらく誰も勝てないと思います(笑)。 そこまで行っちゃって、 一応は満足したんですが、 それでわかったことがあります。 たくさんの写真を撮れば たくさん情報が入ってくるだろう、 だからたくさんの発見ができるだろう、 と思っていましたが、実際は、違いました。 ニューロンのグループ単位って、 おそらく100個とか、 あるいは多くても1,000個くらいなんです。 だから、10,000個撮ってわかったことは、 たくさんのグループがいっぱいあった、 ということだけでした。 神経局所回路の研究をしたいんだったら、 1,000個くらいの規模で十分だった、 ということがわかったんです。 だから、大規模化って、意味があまりない‥‥ やってみてわかったんです(笑)。 |
| 糸井 | そこに行ってみたいという若者の心が そうさせた(笑)。 |
 |
|
| 池谷 | そうなんです。 チリまで行ったら 「ああ、もうそこはおしまいだった」みたいな、 そういう雰囲気がいま、 僕の中にありまして(笑)、 まぁ、がっかりしました。 なかよしグループみたいなニューロンがあって、 それがモザイク状になっている、というのが 脳なんです。 |
| 上大岡 | 脳がそうできてるんだから、 私たちの人間関係も そうなっておかしくないですね。 それぞれのところが少しつながって 活動しているだけで、 全体的な操作は、実はない。 |
| 糸井 | ちょっと前まで、いろんなスポーツで 「データ主義」のようなことが 言われていましたよね。 首脳陣が相手の弱点を分析して、サインを出して それをひたすら破らなければ勝つ、 という発想です。 つまり、選手を身体と考えて、 監督なりコーチなりを脳とする発想です。 |
| 池谷 | 中枢思考主義的なやり方ですね。 |
| 糸井 | ええ。ところが、野球でいうと、 去年田口壮さんがいたフィリーズの マニエル監督は、 ほとんどサインを出さなかったらしいです。 盗塁は、自由だった。 |
| 上大岡 | すごいですね、考えらんない。 |
| 池谷 | 草野球みたいですね。 |
| 糸井 | 盗塁の材料はひとつだけ。 ピッチャーが投球のモーションに入ってから キャッチャーが球を受けるまでのタイムです。 それを、ストップウォッチを持っている 1塁コーチが選手に教えてあげるんです。 ただ、それだけ。 選手は、練習で山ほど走っているわけだから、 自分が何秒でセカンドへ到達できるかを 知っているんです。 そこから計算して、自由に走っていいんです。 |
| 上大岡 | そこで走れという指示じゃなくて、 自分の判断で走れということですよね。 |
| 糸井 | そう。全体の中で、 「ここは走るべきかどうか」と考えるより、 一塁走者が「いまは有利だ」と思ったときには そうに決まっている(笑)。 そうすると、反射神経型の人体のような チームができていくんですね。 |
| 上大岡 | それで優勝したんですものねぇ。 |
| 糸井 | スポーツだけじゃない、いろんな組織にも 同じようなことが言えると思います。 中枢神経だけが命令を出していると、 伝達ロスがありますし、 中枢の人たちがわからない情報を、 現場がものすごく持っているわけですから。 極端に言うと、僕は最近 脳よりも皮膚に興味が出てきてるんです。 皮膚って、まさしく 外界とのインターフェースでしょう。 |
| 池谷 | そういう意味で言うと、昆虫は からだじゅうに脳を分散していますよ。 ハエとか、ああいう虫はそうです。 |
| 上大岡 | え? ああ見えて‥‥。 |
| 糸井 | (笑)ハエはああ見えて、 |
| 上大岡 | 脳がいっぱい。 |
| 一同 | (笑) |
| 池谷 | 心や脳は、頭だけじゃなくて、 むしろ身体あるいは環境全体に 分散しているんです。 皮膚ってけっこう、 僕たちにわからない、いろんなことを 知っているみたいです。 自分の意識がわかってないだけで、 からだのほうがよく知っていることがある、 という現象が、いろんな実験でわかっています。 緊張したりリスクがあるときに 手に汗を握ってしまいますが、 「あ、これはリスクだな」というふうに 僕らが気づく前に、 もうすでに手は汗ばんでいるんですよ。 例えばAとBという、ふたつの選択肢があって、 Aは危ない、Bは大丈夫、 ということがわかるまでは、 何度かトライすることになります。 だけど、Aがまずいとわかる ずいぶん前の選択で、 Aを選ぶときには 皮膚が汗をかいているんです。 一方、僕らは、しばらくしてから 「あ、Aって危険なんだ」ということが 意識としてわかります。 そういう実験結果を見ると、 私たちの脳は、 「皮膚が汗をかいているな」という状態を見て 危険を理解しているんじゃないかとさえ思います。 |
| 上大岡 | 皮膚って、 内臓のサインを出すとも言われますよね。 見えないところの影響が 最初に出てくる。 |
| 池谷 | そうそう。 ですから、触診ができる名医というのは ほんとうにいるんですね。 最近は、そういう名医が減っちゃいましたが‥‥。 |
 |
|
| (つづきます) | |
| 2009-04-07-TUE | |