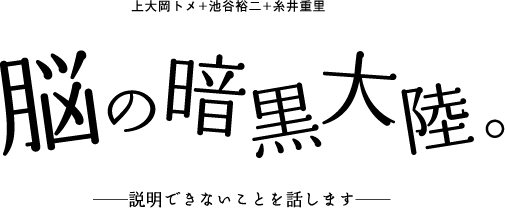|
| 糸井 |
昔の哲学者が言っていることって、
けっこう脳に合っているんじゃないかな、
と思うんです。
自分を棚に上げて立派なことを言ったり、
いいことも悪いことも
同じ快感からやってくるという話は、
ソクラテスが「汝自身を知れ」という言葉で
とっくに言ってることだったりするし。 |
| 上大岡 |
脳科学の切り口は心理学かな、
ということも多いですよね。 |
| 池谷 |
ええ、そうですね。
最近やっと、脳という視点から
心理学の領域について
科学的にアプローチできるようになったんです。
哲学も同じだと思います。
哲学って、すごく難しいことを
やっているように思えるけど、
結局あれは、
一般の人のための学問だと思うんです。 |
| 糸井 |
そうですよね。 |
| 池谷 |
おそらくサイエンスも
ほんとうはそうあるべきです。
だとしたら脳科学は、
科学のなかでも、もっとも
そこに近いのかもしれない。
ここはぜったいやんないといけないな、と
実は思っているんです。 |
| 上大岡 |
それは、脳科学のみなさんが
思っていることですか? |
| 池谷 |
脳科学は、サイエンスの中で
ひとつの形になっているから‥‥
どう言ったらいいんでしょう、
むしろ孤立していたほうが、孤高で美しい、
と考える人もいるかもしれません。
そうするとやっぱり、
日常的なことを説明しようという部分は、
ちょっと外れてしまう雰囲気が、
なくはないんです。 |
| 糸井 |
池谷さんは、そこに近づいていく
勇気のある方だと思うんですが、
それはきっと、サイエンスの分野で
きちんとやっていく土台のようなものを
身につけているからなのでしょうね。 |
| 池谷 |
自分はサイエンスの分野の人間であって、
その作法を知っていて、守るということを
自分の中ではひとつの砦にしているんです。
サイエンスの考え方とか理論の作り方とか、
そういうことです。 |
| 上大岡 |
具体的には、どういう考え方なんですか? |
| 池谷 |
たくさんあるんですが、
いちばんシンプルなことを挙げるとすると、
因果関係を盲信しないことでしょうか。
因果関係はサイエンスではわからない、
ということです。
その点ははっきりしないといけないんです。
例えば、コップに入っている水をこぼしたら、
水がこぼれるのはあたりまえです。
だけど「こぼしたからこぼれた」というのは
サイエンスとしてはダメなんです。
解熱剤を飲んだら熱が下がりますが、
でも、薬をのんだから下がった、
といったらダメなんです。
なぜなら、薬を飲んだから熱がさめたのか、
放っておいてもさめたのかは、わからないからです。
そこを厳密に詰めていかなきゃいけないんです。
論理的に詰めていく段階で、
いろいろややこしい話が出てきて、
結局、因果関係は絶対に
サイエンスではわからないということになります。 |
| 上大岡 |
事実がわからないということですか? |
| 池谷 |
事実と事実の関連がわからないんです。
サイエンスは、
仮説を否定することはできるんですが、
仮説を証明することはできないんです。
反証可能性というんですが、
これが難しいところなんです。 |
 |
| 糸井 |
池谷さんは、そうやってサイエンスを守るし、
サイエンスの世界にいる人たちを
守っているんですね。
サイエンスが危ないところに行く可能性は
いくらでもあるわけですから
そこを、いろんな見方から疑っていこうとする
積み重ねの考え方は、
その次の研究の土台を作っていく、
ということになるのだと思います。
でも、池谷さんは、
ふたつの文体を持っているんじゃないかなと
僕は思っているんですが。 |
| 池谷 |
はい、まったくそうなんです。
基本的には僕は、ほとんどの時間を
サイエンスに割いているので、
ふだんはサイエンスの文体です。
これからあとも大学に戻って仕事するんですが、
そうするともう、話し方までもが変わってしまう。
だけど、みなさんも、
家に帰って奥さんや旦那さんの前で
話すときは、仕事場とは違いますよね? |
| 糸井 |
僕は違わないけど。 |
| 一同 |
(笑) |
| 上大岡 |
だけど、池谷さんは、
よく切り替えて、
私たちのほうに近づいてきてくださいます。 |
| 池谷 |
いや、僕は‥‥、たぶん、
こういうの、好きなんです。
サイエンスも好きだけど‥‥自然界が(笑)。 |
| 糸井 |
池谷さんは、
「ホーム」と呼べる場所が、きっといいところに
あるんじゃないでしょうか。
「どこにいるんですか?」
「ここです」
といえる場所が、
心の中にあるんでしょう。 |
| 池谷 |
そうですね、いい場所もあると思うし、
もうひとつ、飽きっぽいというのも
あると思います。
研究室にいたいと思ったら、
そこがホームだし、
自宅に帰りたいと思ったら、そうじゃなくなる。
ずーっと同じことをくり返すのは、
自分の性格に合わないんだと思います。 |
| (つづきます) |
| 2009-04-03-FRI |