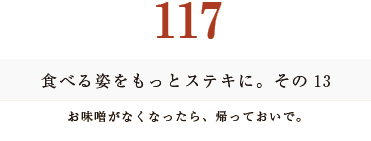 |
|
いやいや。 卵焼きに焼いた鮭。 |
鍋でご飯を炊くのはひさしぶりだから、 「ほっちんご飯」。 広島出身のボクのばぁやさんが使っていた言葉。 砂糖と塩で甘く作った卵焼き。 バターをたっぷり含ませてオムレツを作ったら たしかに料理は食材次第。 |
あぁ、これは‥‥。 今のように国際線の飛行機に持ち込むモノの これはお薬。 ボクはそれから2週間ほどで仕事の引継ぎや、 |
|
| 2012-12-27-THU |
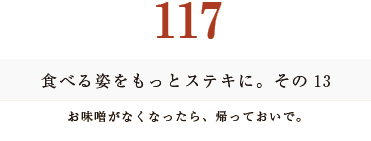 |
|
いやいや。 卵焼きに焼いた鮭。 |
鍋でご飯を炊くのはひさしぶりだから、 「ほっちんご飯」。 広島出身のボクのばぁやさんが使っていた言葉。 砂糖と塩で甘く作った卵焼き。 バターをたっぷり含ませてオムレツを作ったら たしかに料理は食材次第。 |
あぁ、これは‥‥。 今のように国際線の飛行機に持ち込むモノの これはお薬。 ボクはそれから2週間ほどで仕事の引継ぎや、 |
|
| 2012-12-27-THU |