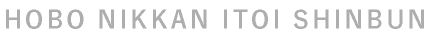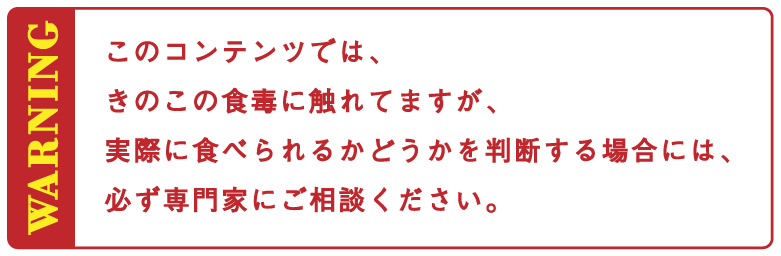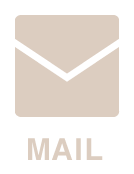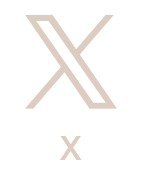ぼくは、きのこの写真を主に撮っていますが、
きのこと同じくらい大自然、特に森が好きなので、
可能な限り、きのこと森の両方が写っている写真を、
撮りたいと常々思っています。
公園やら、庭園やら、ときに道端でも、
きのこの姿を見かけることがありますが、
やはり、自然の森で撮影するのが大好きです。
そもそも、森歩きの気持ち良さときたら!
阿寒湖の周辺では、その昔、
木々が大量に伐採されたことがある森でも、
阿寒湖の大家さんでもある前田一歩園財団によって、
かつての環境を考慮した植樹が行われました。
その後、人の手が入らなくなって80年くらい経つので、
各所で本格的な森の様相を感じることができます。
さて。
今回ご紹介するハタケシメジは、
生える環境がちょっとだけ特殊なので、
大自然の中で生きている!
という雰囲気の写真を撮影しづらいんです、はい。
ハタケシメジは、秋に、
林地、草地、庭園、道端などで発生しますが、
株の根本は、菌糸束となって地下へと伸びています。
なぜなら、地中に埋まった木材から発生しているから。
人の手が入った場所の方が見つけやすいんですね。
傘は、径4〜9cm。
成熟すると、ほぼ平らに開きます。
表面は暗いオリーブ褐色〜灰褐色。
古くなると、やや淡い色になります。
ヒダは、汚白色で、ぎゅっと密集。
柄に向かって、やや長く伸びています。
柄は、長さ5〜8cm。
わずかに帯灰褐色で、上部は粉状です。
数本、またはもっとたくさん、根本でくっつき、
大株になることも珍しくありません。
食。
多少粉臭さがあるものの、美味!
風味はおいしいきのこの代表格ホンシメジに、
決してひけをとりません。
しゃきしゃきした歯触りも独特。
どんな料理にも合うおいしいきのこです。
阿寒湖周辺でハタケシメジを探すとなると、
いちばん手っ取り早いのは、林道脇の草むらの間、
あるいは、木材が積んである土場の跡地が最適。
地下に木材が埋まった場所、と考えると、
探すポイントが絞りやすいいかもしれません。
原生林の中ではあまり見かけたことがありません。
きのこの中では、シティーボーイなのかも(笑)。