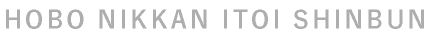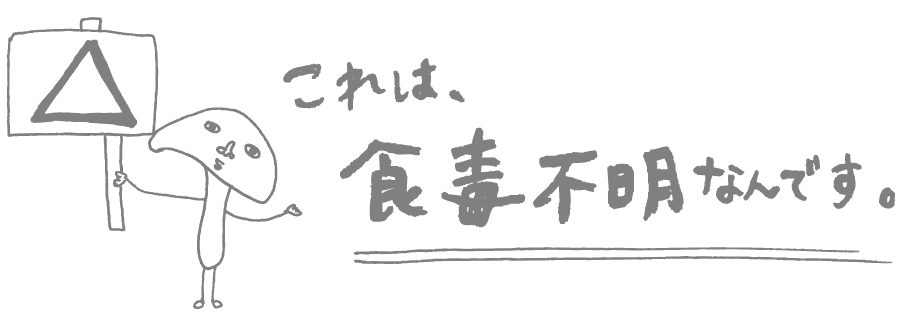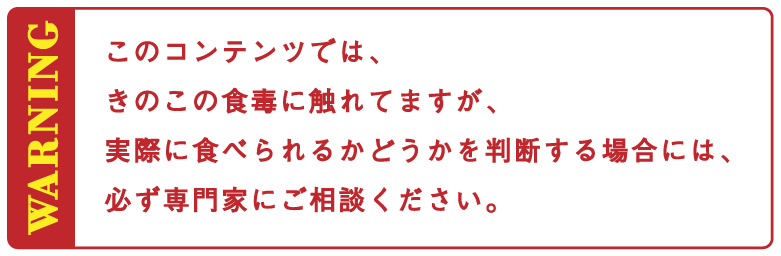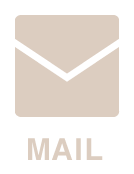春の野山に出かけて、いちばんの楽しみは、
きのこ探し! と言いたいところですが、
きのこシーズンの始まりにはやや早いので、
春の妖精・スプリングエフェメラルと呼ばれる草花の、
鑑賞ということになりましょうか。
雪が解けた落葉広葉樹林の地面に、
カタクリ、キクザキイチゲ、ニリンソウなど、
可憐な花々が一気に咲き、群落をつくります。
白一色だった地面が、赤や白や青など、
鮮やかな色彩で覆われているのをみると、
北国にようやく春が来た!と、感慨深いです。
しかし……。
我々きのこファンは……。
地面に顔をつけるように寝そべって、
太陽の光を受けて燦々と咲き乱れる春の花々を、
じっくりと観察・鑑賞しているかと思えば……。
否(笑)!
美しい花々に焦点を合わすことなく、
草花近くの地面を凝視してきのこ探しです。
カタクリが咲いていたら、
美しい紫色の花ではなく、葉っぱをチェック!
ほら、いました!
緑色の葉っぱの裏側にオレンジ色の点々が。
これこそ、正真正銘の、菌類。
その名も、カタクリさび病菌です。
オレンジ色の粒々の物体を、よ〜く見てみると、
(10倍程度のルーペ使用を大推奨!)
直径1mm以下で、縁が白のちいさな「お皿」が、
たくさん並んでかたまりになっているのがわかります。
拡大するとこんな感じです。

お皿の中と外にある小さな黄色い粒々は胞子ですな。
カタクリさび病菌は、3月頃に宿主植物上に現れ、
4月中旬頃には胞子が入ったいれものを形成。
カタクリの地上部が枯れると一緒に地表へ落ちます。
暑い夏にも寒い冬にも耐え、ひたすら春を待ち、
翌年、カタクリが発芽するタイミングで、
えいや〜と感染するわけです。
食毒不明。
人間には害がないとしても、こんなに小さいし、
カタクリの葉から採集するのは不可能でしょう。
最近では、カタクリは貴重なものだと再認識され、
食用とされることが少なくなっている気がしますが、
(片栗粉はカタクリの地下茎からつくってましたし)
カタクリさび病菌がついている葉っぱが、
食べられるか食べられないかはわかりません!
カタクリさび病菌は、
カタクリの大群落があると探しやすいかも。
ぜひ、花ばかりを愛でるのではなく、
菌類を探して、そして、愛でてくださいませ。
カタクリを愛する人たちにとっては、
カタクリを犯す病原菌なので、
素直に、かわいい、きれい、とは言えないかと。
あしからず。