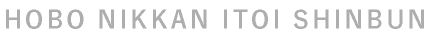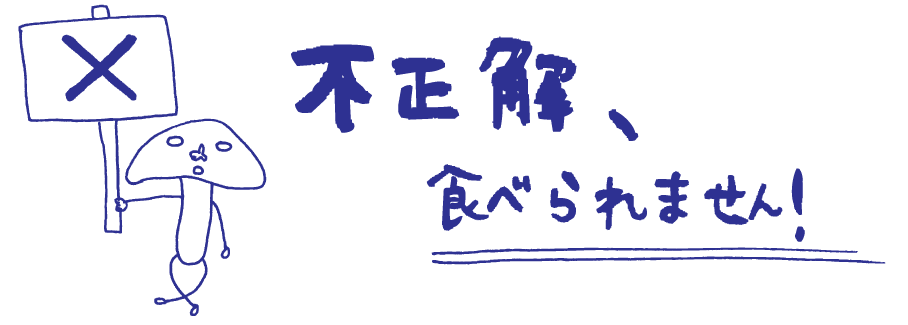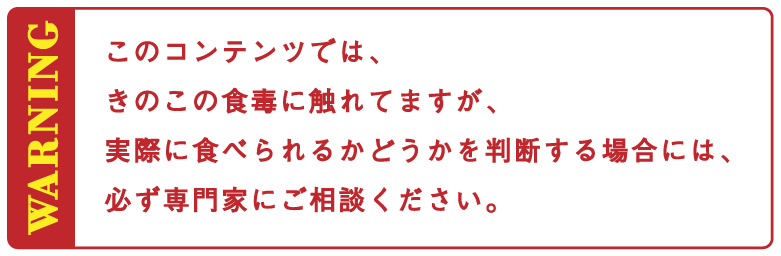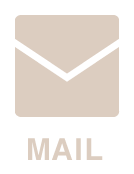雪が解けた後の森の地面は、一面、
雪の重みで押し付けられた、葉っぱ、葉っぱ。
その積み重なった古い葉っぱを突き破って、
緑鮮やかな新芽が伸びています。
春ですな。
人の顔が隠れるほどひときわ大きな葉は、ホオノキ。
ひと冬経過する時間くらいでは分解されません。
「ホオ」の木、ではなく「ホオノキ」という名前です。
ホオノキは成長すると高さ20〜30mにもなる木で、
葉っぱも花も日本では最大級の大きさを誇ります。
(葉は長径20〜40cm、花は直径10〜15cm)
秋になると、森のあちこちに、
トロピカルフルーツと見まごうような、
長さ15〜20cmの長楕円形の、
真っ赤な「実」が落ちているのですが、
これがホオノキの果実(集合果)です。
やがて裂開して種子が現れます。
落葉に埋まったような、
古いホオノキの果実から発生するのが、
今回ご紹介する、ホソツクシタケです。
高さは2〜5cm、細長いひも状、円柱状です。
黒褐色で、径は1mm内外、しばしば1回分岐。
先端は尖っています。
はじめは白色粉状の分生子で覆われており、
熟すと、中央から上が多少太さを増し、
埋没した子嚢殻の凹凸がはっきりわかります。
新しいホソツクシタケは、
初夏くらいから発生するのですが、
硬くて、なかなか腐らないためか、
古くなって真っ黒な状態であれば、
1年中いつでも見ることができるので、
春先のきのこが少ないときでも、
森の地面をよく探せば出会えるきのこです。
食不適。
すんごく硬くてとても食用になるとは思えません。
群生するので、全体に目を配りつつも、
個々のきのこの個性的形状を堪能しましょう。
ちなみに、ホオノキの実、
そして我らがホソツクシタケは食用になりませんが、
ホオノキの葉は芳香があり殺菌抗菌作用もあるので、
食品を包むのに用いられたりしますし、
落葉してもけっこう火に強いことから、
食品をのせて焼く、朴葉焼き、朴葉味噌などが、
飛騨地方の郷土料理として有名です。
直接食べるわけではありませんが……。
朴葉でくるんだ味噌を焚火で焼いて、
日本酒をきゅっと……。
たまりませんな。