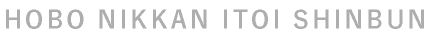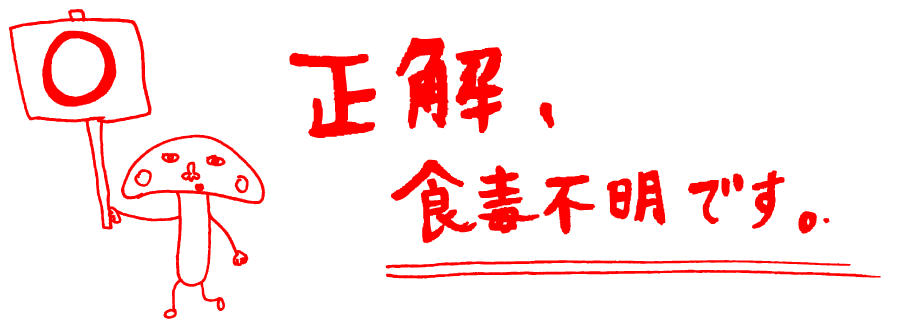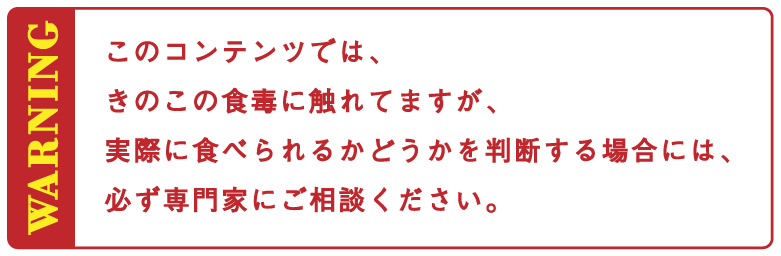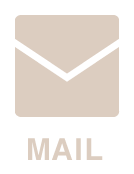かつて、もう30年も昔のことですが、
帯広市で働いていたぼくにとっては、
この、数年に1度レベルの寒気による記録的大雪は、
人ごとじゃありません。
当時も、ひと晩で、
約90cmの雪が降ったことがありました。
(いやあ、雪かきが大変だったこと……)
あと、思い出深いのは、
最低気温マイナス28度が3日連続だったとか。
3日目には、帯広の1/3くらいの車が動かなくなった、
なんて、まことしやかに囁かれたものです……。
日本は四季がはっきりしているし、
それぞれの季節に良い悪いがあるわけですし、
悪い部分はなるべく見ないようにして、
いつでも楽しく過ごしていきたいですよね。
そう言えば、今は亡き、柴犬のはなさんは、
雷が大嫌いでしたが、雷が鳴った瞬間、
布団の間でも、押し入れでも、ぼくの股ぐらでも、
すかさず頭を突っ込んで音を遮断し、
雷を無きものとする方法を編み出しておりました!
と、いうことで、
冬の嵐がやってきている青森の空の下で、
窓から外を眺めず、外出もせず、
雪を無いものと思い込み、
春のきのこのことを考えることにしました。
春告鳥と言えば、ウグイス。
春告草は、ウメ。
では、春告菌は……?
実は、そんなテーマで、過去に、
「きのこの話」の原稿を書いたことがありますが、
何のきのこのことか忘れてしまいました……(笑)。
で、いま、ふと思い浮かべた春のきのこは、
じゃじゃ〜ん、ウラスジチャワンタケです!
このきのこは、春に、
林道脇の地上や公園のブナ科樹木の根本に発生します。
深い茶碗形で、径は5cm前後です。
よく見ると短いですが柄も確認できます。
お茶碗形のきのことしては大きい方かと。
淡灰褐色〜褐色の、お茶碗の表面のすぐ下に、
子嚢と呼ばれる、胞子が入った袋があり、
表面が崩れるとその下側から胞子が放出されます。
そう、いわゆる、子嚢菌です。
お茶碗の裏側と下に伸びる柄の表面には、
隆起した脈状のしわが見られます。
これが名前の元になった「うらすじ」ですな。
食毒不明。
まあ、おいしそうには見えません。
じっくり、観察、鑑賞しましょう。
ちなみに、かつて、茨城県はつくば市にある、
国立科学博物館筑波実験植物園の庭で、
このウラスジチャワンタケをたくさん見つけて、
写真を撮りつつじっくり観察したことがありますが、
うらすじが、マッチョなカンガルーの筋肉に見えて、
笑いが止まらなくなった思い出があります……。
春よ、早く、来い!