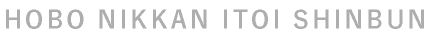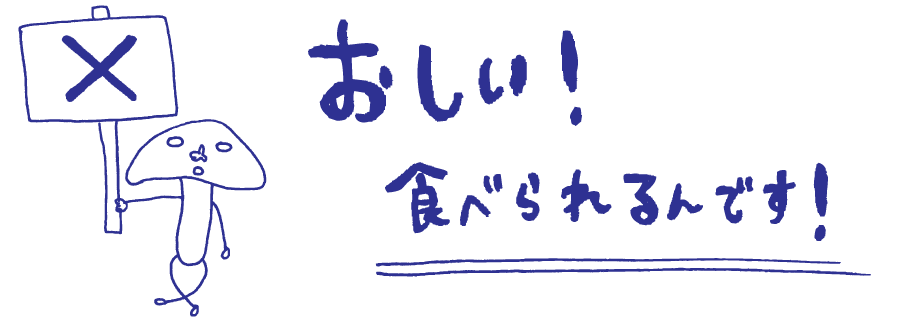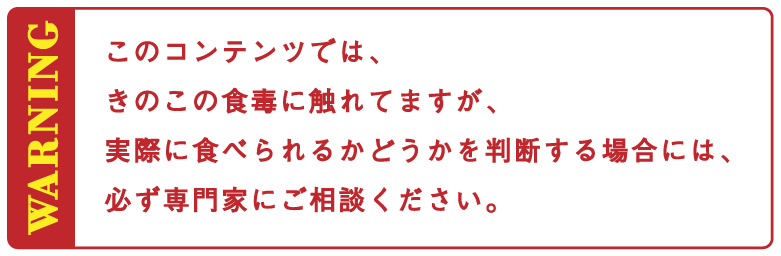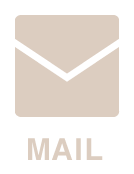一般的には、冬は、きのこ不遇の季節です。
しかし、一般的には不遇であっても、この世の中、
例外はたくさんあります。
冬に咲く桜の花……。
雪が好きなにゃんこ……。
そして、もちろん、
冬に発生するきのこもいます、はい。
冬に見ることができるきのこの代表は、
サルノコシカケの仲間など、いわゆる硬質菌ですね。
触るとカチカチに固い、半円形のやつらです。
サルノコシカケの仲間には多年生のものが多く、
年々、少しずつ、大きくなっていきます。
径30cm以上に成長する大物もけっこういます。
阿寒の森は針葉樹が多いので、冬に、
広葉樹の葉っぱが落ちてしまったとしても、
視界は他の季節とそれほど変わらないのですが、
雪で「地面」が1〜2mほどかさ上げされているので、
視線が高くなった分、新しい発見があったりも。
まあ、きのこが見たい、という期待を抱きつつ、
木々の幹の表面を彩るコケや地衣類を愛で、
小鳥の声を聴きつつ野生動物の足跡をたどり、
雪や氷や霜など冬の自然のアートに感動し、
真っ白な森をゆっくり歩くのは、いいものです。
ほんと、いいものです。
残念ながら、阿寒湖では、
冬に見たことがないのですが、ほかの地域では、
冬に見ることが多いきのこがいます。
ヒラタケです。
ヒラタケは、秋から春にかけて、
低地〜山地の広葉樹の枯木や倒木に、株状に発生。
針葉樹から発生することもあるようです。
乾燥してかちかちに乾いた姿もよく見かけます。
傘は径5〜15cmほど、貝殻形〜半円形〜丸山形で、
のちに平らに開きます(中央がややくぼみます)。
初めは青味を帯びた黒色〜灰色で、
開くと次第に色が淡くなっていきます。
傘の裏のヒダは白色、あるいはやや灰色を帯び、
柄に向かって長く伸びています。
柄は短く、白く、傘から偏心することが多いです。
食。
歯切れも、風味もいい、優秀な食菌で、
人工栽培したものをお店で買うこともできます。
冬にも採集できることから、
「寒茸(かんたけ)」との呼名もあるようです。
東京あたりでは、
そろそろスギ花粉が飛び始めた、
なんてニュースを聞きますが、
こちら、北国では、まだまだ冬の真っ最中。
春がやってくる前に、もう少しだけ、
冬の森を楽しみたいと思います。