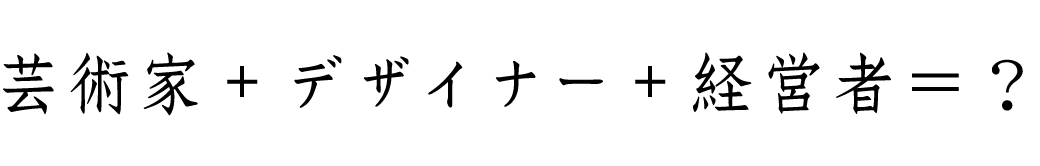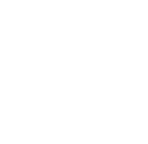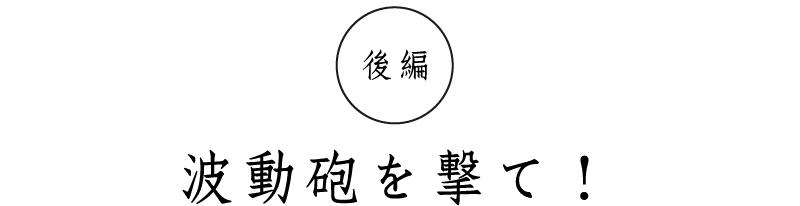
アートという「不可解なもの」を吐き出し、
それらを分類して整理し、
ロジックを使って、
マスプロダクト=商品として「設計」する。
スタッフさんを雇い、給料を払う。
そういう人のことを、何と呼んだらいいのか。
それは、小田さんが知りたいと思った、
「芸術と経営の間のバランスの取り方」にも
関係してくると思いました。
他方で、そういう難しいことは抜きにしても、
生み出している物体の、
なんとも言えない、不可解な魅力も相まって、
土佐さんというアーティストや
「明和電機」という組織の成立のしかたに、
どんどん興味が湧いてきました。
- 小田
- たとえば(覆面芸術家の)バンクシーみたいに、
匿名性で神秘性を増幅させるような
アーティストもいますけど、
土佐さんの場合、その真逆をいってますよね。
- 土佐
- はい、「見てのとおり」です。
- 小田
- それって、アーティストとしては、
ちょっとリスクないですか?
- 土佐
- あ、そう?

- 小田
- つまり、明和電機のライブを見ても、
「ありがたいアート作品を鑑賞している」
という感じにならないと思うんです。
- 土佐
- ならないでしょう。
- ──
- なにしろ
ライブのことを「製品プロモーション」と、
おっしゃっているくらいですものね。
- 小田
- そういう意味での「リスク」です。
ぼくらデザイナーからすると、
作ったものをみんなに理解してもらう努力って、
ものすごく重要なんですけど。
- ──
- たしかに土佐さんは、
まず、第一義的にはアーティストですけど、
「不可解」を「商品」に落としこんだり、
ライブや展覧会として展開する場面には、
設計者と言いますか、
とてもデザイナー的な冷静さを感じます。
- 小田
- でもそうか、きれいに設計するだけじゃなく、
土佐さんの場合は、
かならず「不可解」を残しているから‥‥。
- 土佐
- ぼくがつくっているのは「道具」なので、
「使用場面」を見せてなんぼ、
ということが、まずは、ある気がします。
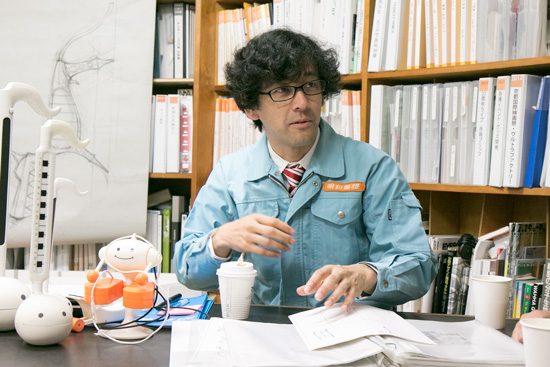
- 小田
- なるほど。
- 土佐
- でも、つくりたいのは、
やっぱり「ナンセンス=マシーン」なんですよ。
ナンセンスな機械をつくるのがテーマなんです。
ただ、やっていくうちに、
どうやったって、
「本質的にナンセンスな機械」なんてものは、
人間には作れないことがわかりました。
なぜなら、機械というものは、
人間の理解が及ぶ範囲でしか作れないからです。
- ──
- 人間の限界を超える「ナンセンスな機械」を
作ることは、不可能であると。
たしかに機械というのは、
動くこと自体が、ロジックの産物ですものね。
- 土佐
- その点、人間をはじめとした生物は、
機械以上の「不可解」をたくさん持ってます。
だから、どうやったって
「自分以下のナンセンス」ができてしまう。
ぼくは、あるときに、
決定的にそうなんだとわかってしまった。
でも「ナンセンス=マシーン」は、作りたい。

魚が世界をノックする装置。
水槽内で回転するレーザーを魚が遮ると、その真下のノッカーが動く。
- ──
- どうするんですか。
- 土佐
- たどりついたのが
自分の作った「ナンセンス=マシーン」を、
「製品プロモーション」として、
次々に見せていくライブをやることでした。
つまり、
わかりやすく「不可解」を伝えてあげる。
自分という生物がそこに介在することで、
「うわ、ヘンなことやってる」
「あぁ‥‥ナンセンスだなあ」
という感覚を共有できると思っています。

- ──
- 機械だけだと、いくらナンセンスでも、
「よくできてるね」って話になってしまう。
- 土佐
- そうですね。で、飽きます絶対。見てて。
そもそも、ライブをやっていて、
いちばんウケる場面は、「故障」ですし。
- ──
- そうなんですか(笑)。
まったくロジカルとは反対の現象ですね。
- 土佐
- 毎回、自分で念入りに整備して、
今回は絶対に大丈夫だと思っているのに、
ライブだと、なぜか、
思いもしないような事故が起きるんです。
そのとき、自分の中の創造力が、
「ゴーッ!」と、掻き立てられるんです。
- ──
- おお。
- 土佐
- 「これを、あと1分で直さなあかん。
お客さん全員、こっち見てる!」

- ──
- ステージ上で修理するんですか?
- 土佐
- そうです。その場で直すんです。
なんでしょう、あの、燃える感じは。
- ──
- 壊れないライブもあるんですか?
- 土佐
- ありますが、壊れなかったライブでは、
お客さんからブーイングを頂戴します。
- ──
- 「なんだよ、壊れないじゃないか!」と(笑)。
- 土佐
- ぼくらのほうも
「うーん、壊れなくて、よかったねえ‥‥」
みたいなモヤモヤが。
- 小田
- 壊れなくてよかったけど、
壊れなかったからよくなかった‥‥って(笑)。
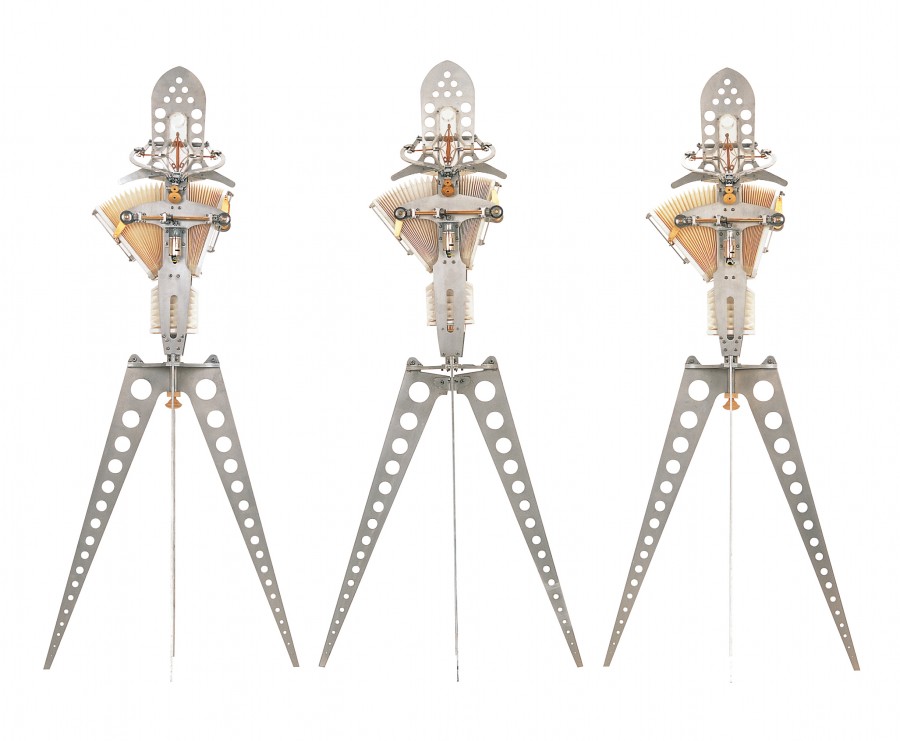
ゴムでできた人工声帯にふいごで空気を送り、
張力をコンピュータ制御することで、歌を歌う装置。
三体あり、それぞれの名前は
「アン(Anne)、ベティ(Betty)、クララ(Clara)」
工員さんは「船の乗組員」である。
それではあらためて、
明和電機という、きわめてまれな会社?
組織? チーム? 集団? 中小企業?
‥‥の「経営」にあたって、
デザイン的なるものは、
どんな場面に顔を出してくるのでしょう。
- 小田
- ちょっと前に、ここにいるみんなで、
大分の三和酒類という、
焼酎の「いいちこ」をつくっている会社へ
取材に行ってきたんです。
- 土佐
- あ、いいちこ。
- 小田
- アートディレクターの河北秀也さんと
二人三脚でポスターを作ってきた、
名誉会長の西太一郎さんに、
いろいろと、お話をうかがってきて。
- 土佐
- おお、名誉会長。
- 小田
- 三和酒類さんでは、会社の中にも、
いいちこのポスターを貼りまくっていて、
会社の標語のようになってました。
つまり、デザイン的なメッセージなのか、
会社のメッセージなのかが、
わからなくなるくらいのところまで、
「デザイン」が
「会社の経営」に入り込んでいたんです。

- ──
- 実際、いいちこのポスターは、
お客さまに向けたものであると同時に、
三和酒類の経営陣や社員に向けた
メッセージにも、なっているそうです。
- 小田
- でも、明和電機の場合は
「土佐さんと誰かの二人三脚」というより、
はじめの「ゲェー!」からはじまって、
土佐さんひとりで手を動かす範囲が
広いと思うんです。
アトリエにはスタッフもたくさんいるし、
なにより
中村(至男/アートディレクター)さんが
デザインで関わっていますけど、
「じゃあ、みなさん、あとはよろしく!」
というより、土佐さんが、
最後まで見ている印象があるんです。
- 土佐
- 不可解なもの、情念、アート。
それらを外に吐き出すための第一ステップは、
たとえば「絵を描く」ですね。
そこまでは やっぱり自分のテリトリーだし、
自分から剥ぎ取れないものです。
で、その次のステップは、
吐き出した情念を、理性でビシバシ叩くこと。
ナンセンスをコモンセンスで叩くと言っても
いいと思うんですが、
つまり、それが「設計」ってことだと思う。

- 小田
- なるほど。
- 土佐
- そのときに使うのは「論理」です。
で、そこは、別の人に預けられると思ってる。
自分が死んでも外注すればできるし、
逆に、それを見たいという気持ちがあります。
自分の吐き出した「不可解」が
「普遍」や「常識」によって叩かれることで、
より「強度」を増してゆき、
たとえば「伊勢神宮」じゃないですが、
ずっと残るような普遍性を持つ。
そのさまを見たいという思いは、あります。
- ──
- つまり他人の存在が重要ってことですか。
先ほど、土佐さんは、
スタッフさんのことを「工員さん」って
呼んでおられましたが、
みなさんのことは、どう思っていますか?
たとえば、
チームメイトとか、弟子とか、戦友とか‥‥。
- 土佐
- 船の乗組員。

- ──
- おお!(ほぼ日と同じ‥‥)
- 土佐
- 昔から、そういう意識があります。
- ──
- なぜですか?
- 土佐
- 明和電機は、すぐに沈んじゃうような
「ちいさな船」なので、
自分の持ち場を、きっちり守ってほしいんです。
誰かがピンチになって、
他の誰かが持ち場を放棄して助けに行ってたら、
船がもろともに沈んでしまうでしょう。
大きな企業の場合は、
他の誰かに取り替えが効いたり、みたいな
「安全策」があると思うんですが、
明和電機では、
それぞれが持ち場の「エキスパート」になって、
船を前に進めて行かなければならない。
その点は、わりと厳しく‥‥というかなあ、
まぁ、よく言ってることですね。
- ──
- じゃあ、土佐さんの役割は「船長」ですね。
- 土佐
- そうです。「波動砲を撃て!」
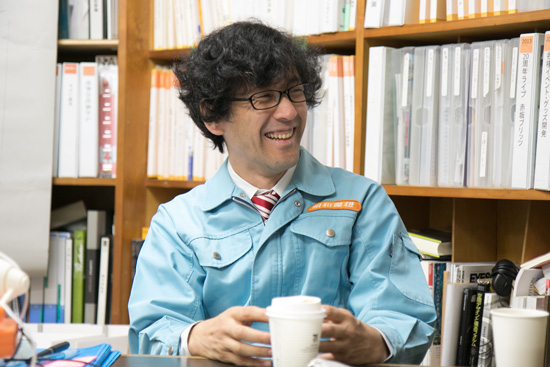
- ──
- ちいさい船の割には
ずいぶんな武器を積んでるんですね(笑)。
- 土佐
- 工場の雰囲気が「船っぽい」っというのも、
ひとつ、あるとは思います。
ぼくが「吐き散らしたもの」を加工して、
できあがったものを溜め込む倉庫があって
それらは、いずれ出荷されていく‥‥。
- ──
- 工員さんは、
どんな基準で採用してるんですか?
- 土佐
- そばにいて、おもしろい人。
- ──
- 明快ですね。
- 土佐
- おもしろくないと、刺激を受けないから。
ぼく、工員さんから、
ものすごく影響を受けるんですよ。
たとえば、
演劇好きな工員さんがいたりすると、
演劇の仕事が増えていったりするんです。
- ──
- はたらく人の個性によって、
仕事の幅も増えていく、みたいなことが。
- 土佐
- ありますね。ここでは。

乗組員として迎え入れる人しだいで、
船の姿が、生き物みたいに変わっていく。
結果、船の針路も微妙に変化し、
また新しいものが、生み出されていく。
そんなイメージが浮かびました。
アーティストとしての土佐信道さんが
吐き散らす「製品」のリストには
たとえば
「エンジンで駆動する、
すべての歯がナイフに化したアゴを持つ、
金属製のプードルの頭」
みたいな、マグマのほとばしりのような、
まさに「不可解」としか言えないものが、
ズラリと並んでいます。
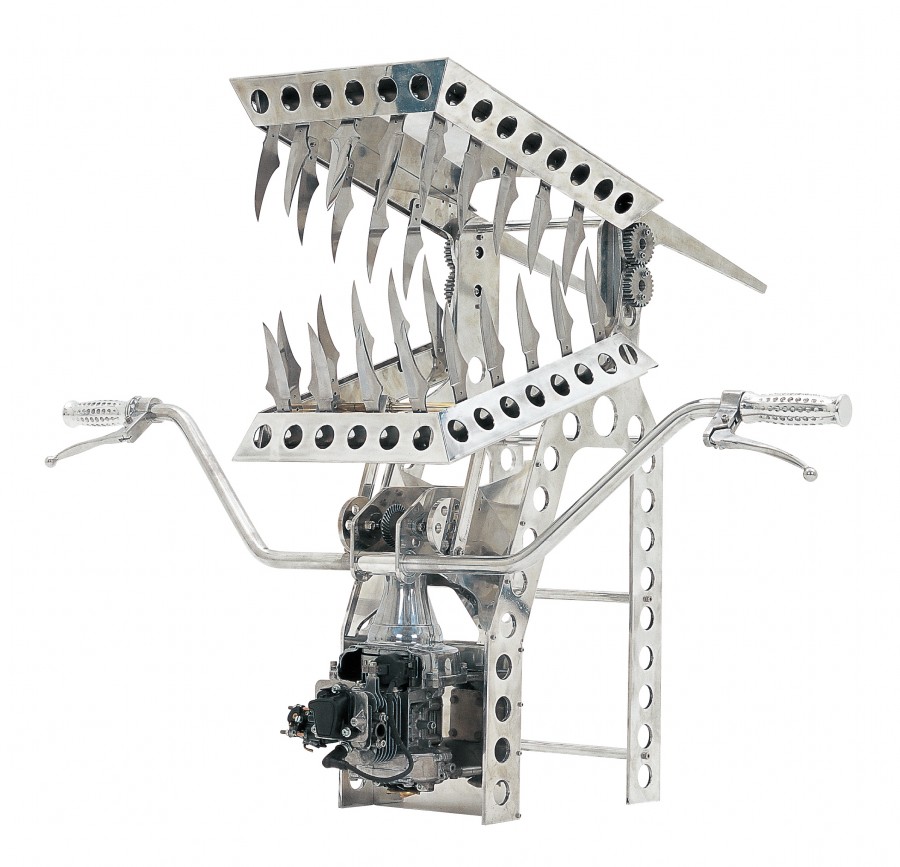
でも、そこから商品を開発する過程では、
一転して「醒めた、論理的な土佐さん」が、
売るために必要な要素を
冷静に判断し、かたちにしていました。
不可解やナンセンス、アートに対する、
論理、コモンセンス、冷静さ。
第一にアーティストでありつつ、
商品を設計するデザイナー的な側面もあり、
人を採用し、
給料を払っている経営者でもある。
場面場面によって、求められる役割の間を、
ゆるやかに「三変化」しながら、
船長の土佐さんは、
明和電機という船を前に進めている。
芸術家+デザイナー+経営者=船長。
土佐さんは、まさしく
「波動砲を撃てと言う人」とお呼びするのが
いちばんふさわしいと思いながら、
展覧会の追い込みで鉄火場であるはずなのに、
たいへん整理整頓されたアトリエを後にしました。

<終わります>
2015-11-27-FRI