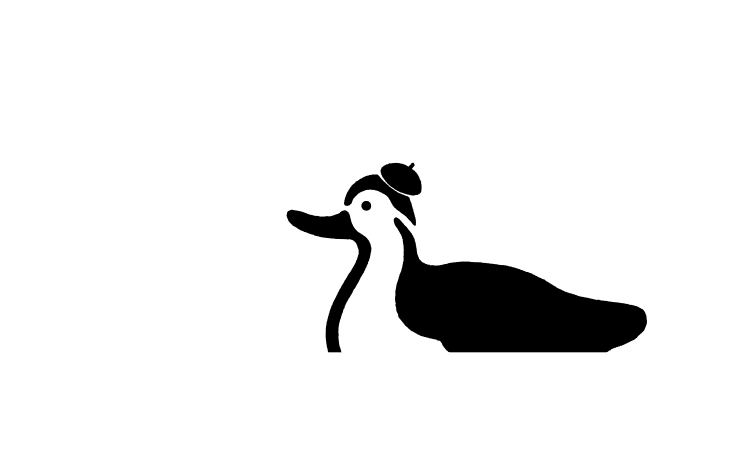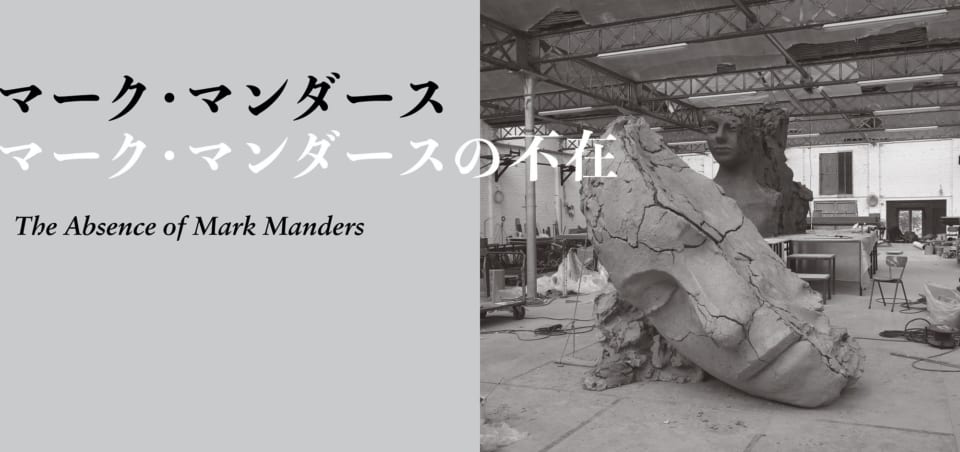この展覧会で、
「物」がたくさんのパワーを持っていること
はじめて意識しました。
ベルギーを拠点に活動されている作家、
マーク・マンダースさんの国内美術館では初となる
個展「マーク・マンダース -マーク・マンダースの不在」へ行きました。
「建物としての自画像」というアイディアを軸に、
自身とは別人である、架空の芸術家として名付けた、
「マーク・マンダース」という人物の自画像を
「建物」の枠組みを用いて構築しています。
単体でも十分に魅力的な彫刻やオブジェたちの、
配置で人の像を表現していて、展示全体が
ひとつのインスタレーション作品となっています。
 ▲乾いた土の頭部( 2016-2017)
▲乾いた土の頭部( 2016-2017)
と、ひと通り説明しましたが、
この独創的な構造の作品世界をお伝えするには、
まず、マンダーズさんご本人の
メッセージを読んでいただくのが良いと思いました。
それがこちらです。
——————————
「物は最も強い瞬間を
とらえることができるものだと思う。
感染症、戦争、季節…と、移り行く世界の中で
物はそのままの状態であり続けます。
私が芸術を本当に愛する理由はそこにあると思っています。
200年前と今とで作品の見方は違ったとしても、
その作品自体は変わっていません。
物が同じに留まっているということは、とても美しい。」
「物を作ることで時間を共有することができるし、
共通点を見出すことができます。
エジプトやギリシアの彫刻には、
様式化されたような、凍結した時間があります。
動きを止めるというようなローマの彫刻とは異なる時間が。」
「実際の物を使って書くことができていて良かったと思っています。
紙に書くのではなくて。
これをやればやるほど、物の言語というものが
非常に重要であると確信するようになってきました。
例えば、彫刻や物を見ると時には
作り手の頭の中や心の中を翻訳することができます。
そういうものは、言葉そのものよりも
ダイレクトに語りかけてくると思います。」
——————————
 ▲マインド・スタディ(2010-2011) ボンネファンテン美術館蔵
▲マインド・スタディ(2010-2011) ボンネファンテン美術館蔵
今回の展示では、個々の作品には
キャプションなどは全くついていませんでした。
(ハンドアウトで作品名や材質は知ることができます)
言葉の情報が無いことで、作品そのものと
直接向き合っている感覚が強かったです。
マンダースさんのメッセージを読んで、それが
「物の言語がダイレクトに語りかけてくる」
という体験だったことに気がつきました。
そして、全体を通して
物の言語は言葉よりも饒舌であることを知りました。
 ▲5の箒(2001)
▲5の箒(2001)
私は、展示室を進みながら、
マンダースさんが、作品で構築している
「人の像」は、そもそもどんなものだろう?と考えていました。
すると、人間の存在は
様々な要素が、複雑に積み重なって
生み出されているものだ、という考えが浮かび、
そしてそれを、言葉で表現しきるには限界があることも感じました。
私にしても、ほぼ日で働いている一面もあれば、
家で猫をナデナデしている一面もあります。
さらに、もっと奥の方には
いろんな経験や感情が隠されています。
悲しい別れや、嬉しい出会い、
志や、夢みていること、
漠然とした不安や焦燥感、そして自尊心。
自分しか知らないこともあれば、
自分以外が知っていることもあります。
たくさんのあれこれが、
対立しながらぐるぐると渦巻いて、
私を形作っている気がしています。
そんな、言葉にしきれない人間の複雑な要素が
マンダースさんの彫刻やオブジェには、
内包されているようでした。
 ▲4つの黄色の縦のコンポジション(2017-2019)
▲4つの黄色の縦のコンポジション(2017-2019)
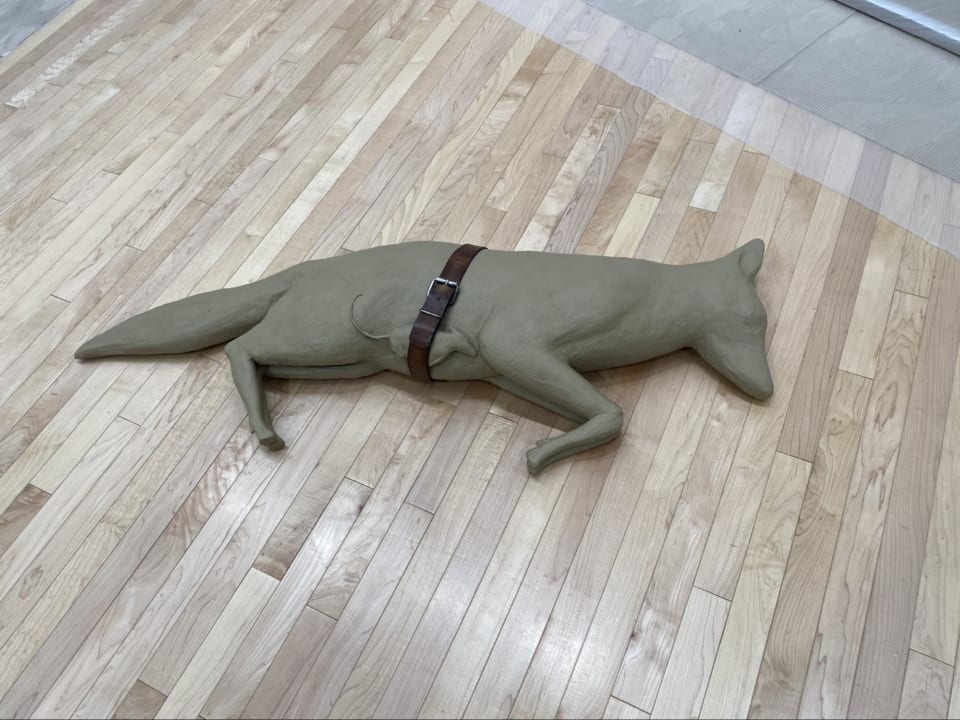 ▲狐/鼠/ベルト(1992-1993)
▲狐/鼠/ベルト(1992-1993)
マンダースさんの彫刻やオブジェは、
それぞれが全く異なる様々な性質を持っています。
今作ったばかりにみえる粘土の艶と、
風化して脆く崩れ落ちていまいそうな質感、
ピンと張り詰めた糸と、弛んだ糸、
それらには、力強さと脆さ、緊張と緩みなど
対極にあるようなイメージが湧きましたが、
一人の架空の芸術家を構成する物として配置されているのです。
私の中でいろんな経験と感情が
ぐるぐると対立しているのと似ていて、
架空の芸術家マーク・マンダースの存在に説得力を感じました。
 ▲細く赤い文の静物(2020)
▲細く赤い文の静物(2020)
私はこの、展覧会でマーク・マンダースさんのことを知りました。
物がもつ魅力を自分の感覚を頼りに感じる展覧会で、気がついたら、とても大きく、ユニークなこの世界の虜になりました。
まだまだ、お伝えしたいことはありますが、
その魅力は、やはり言葉では書ききれません。
会場に足を運んで、架空と現実が混交する
不思議な世界を体験してみるのはいかがでしょう。