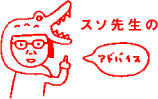|
|||
|
|||
来客にミシンの面白さを力説するのを 最近の楽しみにしているたかしまです。 (被害に遭った方、スミマセン) いよいよ大詰めの今回も どうぞよろしくお願い致します。 さて、ミシンの扱い方にも慣れてきたので 本番の布を縫ってみることにします。 まずは買い集めたそれぞれの布から 型紙どおりにパーツを切り出します。  そしてミシンの登場です。 猫帽子の本体部分のパーツを縫い合わせていきますよ。 仮の帽子をスレキでつくったときと同じように てっぺん部分から順番に縫い合わせます。 フェイクファーでつくった耳は 生地が厚すぎてマイミシンでは縫えなかったので、 あとから手縫いでくっ付けることにしました。 なので、耳を挟めるだけの隙間を残しておくことを 念頭におきながらミシンを踏みます。 練習の甲斐あってミシン操作は我ながらスムーズ! スムーズすぎて、案の定耳の隙間を残すのを忘れて 縫い合わせてしまった失敗も正直に報告しておきます。 ミシンの縫い目はきっちりしている分、 失敗した糸を取り除くがけっこう大変でした。とほほ。 そうそう、縫い合わせながら 7mmの縫い代部分はこまめにアイロンで 左右にペタッと開いておきます。 そうしておかないと 裏地を縫い合わせるときに邪魔になってしまうのです。 この縫い代を“割る”作業は 割台という帽子用のアイロン台があるとやりやすいと スソ先生の著書に紹介されていたので、 木の丸椅子を横にして代用してみました。   慣れないアイロンの作業にちょっと時間がかかった他は さすがミシン様、あっという間に 本体パーツの縫い合わせは完了です。 あとは仮の帽子のときの要領で耳を手で縫い付ければ…  おー、なんか帽子みたいじゃないですか。 ちゃんとできてるっぽいじゃないですか。 来ました、ついにここまで来ましたよ。 スソ先生に見てもらうのを楽しみに思いながら、 しばし冠ってみたり脱いだりを 満足げに繰り返したのでした。 と、以上が今回の教室前日のできごとです。 縫い合わせた本体(耳付き)を うれうれとスソ先生にお見せしてみると、 「ちゃんと帽子になってますねー」と お褒めの言葉をいただきますますホクホク。  今回は顔などのパーツの縫い付け方や 裏地のつくり方など、 完成までの残りの手順に関する疑問点を あれこれまとめて教えていただきました。  帰ったらマイミシンでやってみまーす!
|
|||