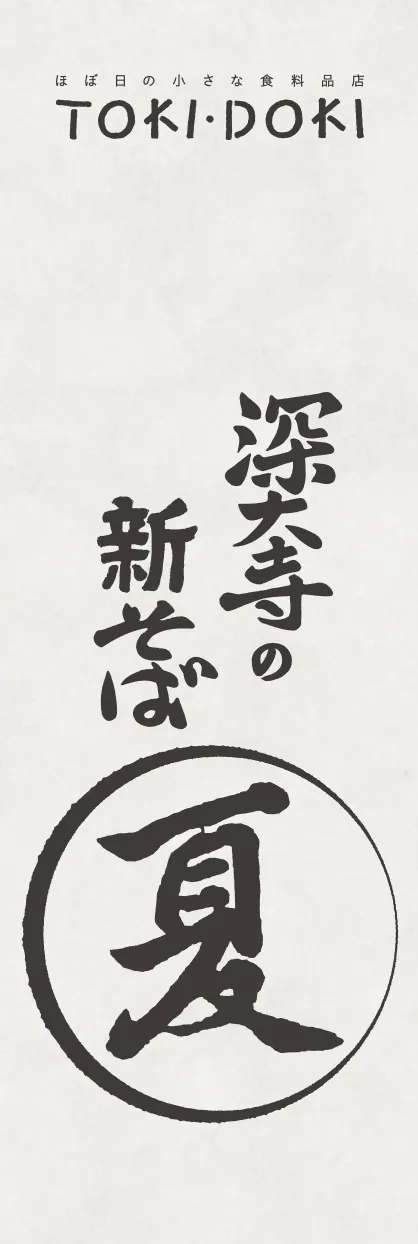
おいしいものを、その時々で。
そんな気持ちをこめて
「ほぼ日の小さな食料品店
TOKI・DOKI」(ときどき)をオープンします。
「ほぼ日」の食品チームが見つけたおいしいものを、
仕入れて販売するネットのお店です。
そんな「TOKI・DOKI」の第一弾は
「深大寺の新そば 夏」。
深大寺(じんだいじ)というのは東京の西部、
調布市にある天台宗のお寺です。
創建733年、東京では浅草寺(せんそうじ)に次ぐ古刹。
深大寺周辺は国分寺崖線(がいせん)のすぐ下に位置する
湧き水が豊かなところで、
朝霞がたち、昼と夜の温度差が大きい、やせた土地です。
そんな環境がそばの栽培に適していただけでなく、
豊富な湧き水は水車の動力となり製粉に使われ、
そば打ち、釜ゆで、晒し水にも使われました。
ふるくはわさび田もあったことから、
深大寺周辺は江戸時代から
関東では有数の「そばの産地」になり、
上流階級のひとびとに愛されたといいます。

江戸の前・中期までは、一般庶民には縁遠かった
深大寺のそばですが、
文化文政年間になり武蔵野を散策する文人墨客に愛され、
ごく一部の上層階級のみのものから、
庶民へと広まっていきました。
時を経て文久年間(1861~64)深大寺の門前町に
最初のそば屋「嶋田屋」が開店。
その後、今はなき「時雨茶屋」が開店。
以後、そば屋が増え、今では20数軒のそば屋があり、
参拝の行き帰りに
打ちたて・茹でたてのそばを食べるのが
観光のたのしみになっています。

この深大寺そばの「そば粉」を
一手につくっている会社があります。
大正時代から深大寺周辺でとれたそばの実を
粉にする仕事をはじめた「島田製粉」です。
深大寺周辺でそばの栽培が行なわれなくなったいまでも、
厳選した国産のそばの実を集め、
石臼挽きでそば粉をつくり、
深大寺そばの各店に納品している島田製粉は、
同じそば粉で乾めんや生めんの製造もおこなっています。
「ほぼ日」は、縁あって知りあった
島田製粉の社長である島田栄造さんから
「夏の新そば」の存在をききました。
新そばといえば、秋口からのもの。
でもほんの少しだけ、秋田と栃木でとれる
夏の新そばがあり、そのほどんどが
直接、おそば屋さんに納品されてしまうのだそうです。
(なので、ごくまれに、おそば屋さんでは
夏の「新そば」を食べることができます。)
まず乾めんにはならない「夏の新そば」ですが、
島田さんのところに、
品評会に出すために少しだけつくった
「夏の新そばの乾めん」がありました。
夏の新そばの特徴は、
きれいな薄黄緑色と、よい香り。
一般にはほとんど販売されないこの「夏の新そば」を、
「TOKI・DOKI」に分けていただくことになりました。

島田さんに、ゆで方・晒し方・盛り方もききました。
深大寺そばならこれ、という
「ちょっと甘くて、そばをたっぷりくぐらせて食べる」
つゆをいっしょに販売します。
茹でるところから、
しっかり冷たくして盛りつけるところまで、
みなさんにはちょっと手間をかけますけれど、
どうぞ、味わってみてください。
