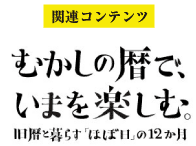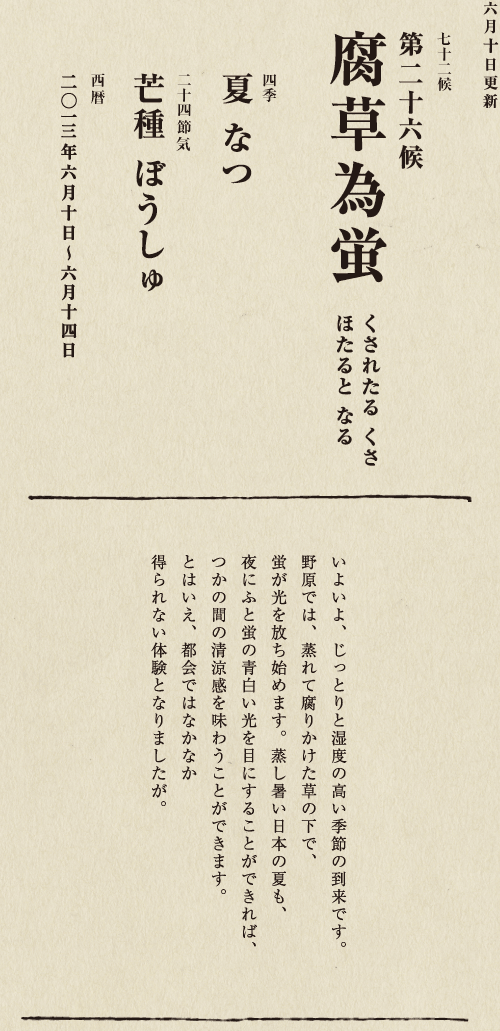
| ── | うわぁ、これはなんだか。 |
| 字がすごいですよ。 |
|
| ── | 「腐草為蛍」。 |
| まさに湿気の世界。 ジメジメ‥‥。 |
|
| ── | 「蒸れて腐りかけた草の下で、 蛍が光を放ち始めます」と。 もうこの頃に蛍が出るんですね。 そういえば、先日三重県の伊賀に行きましたが 「蛍が1匹だけ出ていた」と 話題になっていました。 東京だとどこでしょうねえ。 山縣有朋の邸宅だった‥‥。 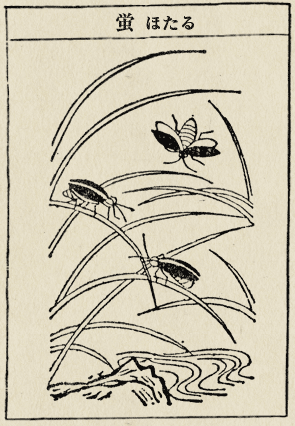 |
| 目白の椿山荘! |
|
| ── | いま調べましたら、5月17日に、 ことしの蛍の初飛翔を確認したと 記事になっていました! |
| 夏の印象がありますけれど、 意外と早いものですね。 |
|
| ぼくが行ったことがあるのは 横浜の三渓園です。 きれいでしたよ。 |
|
| いいでしょうねえ。 しかし、放しちゃった蛍は 逃げますよね? |
|
| その時期はそこに いるんじゃないですか。 渓谷みたいになってますからね。 |
|
| ── | でもあんまり街には 飛んで来てないですね。 見たことないですよね。 |
| もし街に飛んで来ても、 光らないんじゃないですかね。 真っ暗じゃないと。 |
|
| ── | ああ、都会は。 |
| なるほど~。 |
|
| ── | 東南アジアの田舎に行くと 年がら年中飛んでいるという情報も。 |
| テレビで木を見たことがあります。 蛍の木。 |
|
| 明滅するのがシンクロするんですよね。 |
|
| そうそうそう。 |
|
| ── | ピカピカっていうのが どんどん一致していって。 美しいでしょうね。 |
| 巨大なクリスマスツリーのような。 |
|
| ── | 弊社の茂木が、ボルネオ島の川下りを 夜、体験したときに、 蛍がとまる木を見たそうです。 彼女の情報によれば、インドネシアのバリ島で 外国人の女の子を現地の男の子が デートに誘うときの口説き文句は 「クナンクナン(蛍)を見に行かないかい?」 だそうです。 |
| 雅なイメージがナンパの道具に! |
|
| でも、効くと思いますよ、絶対。 「LED見に行こうか」って言われてもね。 |
|
| ── | よく言えば、山田詠美の世界ですよね。 バリ島豆知識でした。 国内で「蛍を見に行く」となると、 滋賀県米原市の天野川流域の源氏蛍、 これは国の特別天然記念物だそうです。 宮城県登米市の鱒渕川の源氏蛍も 国の天然記念物。 都市部では京都の哲学の道、 東京世田谷の岡本公園民家園などが たのしめます、と書かれています。 |
| いのち、短いんですよね。 |
|
| ── | 寿命は1年で、 ほとんど水中にいるんですが、 成虫になって美しい光を放つのは わずか1週間だそうです。 |
| じゃ、その間に相手を見つけなきゃ いけないんだ。 |
|
| ── | 蝉と一緒ですねえ。 蝉より短いか、1年だったらね。 さて、季節の魚は「伊佐木」。 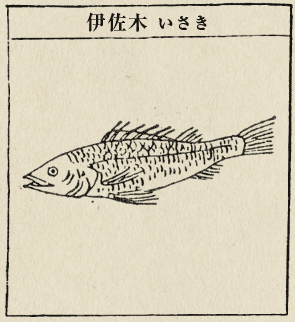 |
あんまり聞かない‥‥っていうか |
|
| ── | 伊佐木の唐揚げ、とかいいますけどね。 鮎にも似たきれいな形ですね。 尻尾が赤いですね。 |
| なかなかこうやって 漢字で見ることも珍しいですよね。 |
|
| ── | 『伊勢佐木町ブルース』を‥‥。 |
| そうなんですよ(笑)。 漢字で見るとどうしても 伊勢佐木町を思いだします。 |
|
| ── | ♪ドゥドゥビ ドゥビドゥビ ドゥビドゥヴァー♪ |
| 「鶏魚」とも書くらしいですよ。 |
|
| ── | 「体は長い紡錘形で口は小さく、 背部は蒼褐色。 腹部には淡黄色を帯びる。 海藻の多い近海の岩間にすみ、 体長は30センチくらい。 初夏が殊に美味」と。 |
| 焼き魚、唐揚げ、煮付け。 |
|
| ── | 魚屋さんというか、 我々はスーパーにしか行きませんが あまり見ない魚ですね。 「主に一本釣り」、 ということはけっこう大変ですね。 |
| 貴重な魚なのかな。 |
|
| ── | 今やね。 |
| 高いということですね。 |
|
| ねえ。 |
|
| ── | 成魚は45cmだって。 |
| でか! |
|
| ── | 一方「縞鯵」も旬でございます。 こちらはもうポピュラー。 |
| これはもう寿司屋でよく見ますよ。 |
|
| ── | 黄金色の縦縞があるので縞鰺と。 |
| 鰺にしてはでかいですよね! |
|
| ── | 成魚は最大で‥‥。 |
| 1m! |
|
| ── | え、でも鰺? |
| 鰺の仲間のうち、とは書いてますね。 |
|
| ── | 鰺なんだ! |
| こんなでかい鰺いるんだ(笑)。 |
|
| ── | 鰺といいながら、鰺じゃないのかと 思ったら鰺でした。 アジ科、アジ亜科、シマアジ属。 |
| シマアジ属! でか! |
|
| ── | しかも高級魚ですよ。 青魚というより、 白身魚の印象ですね。 |
| そうですね。 脂もすごくぷるんぷるんと。 |
|
| ── | 「水深200m付近までの 浅い海に生息する」。 浅い海に住みつつ、でかいのか! |
| 食べでがありますね(笑)。 |
|
| ── | 開きにとかはしないでしょうね、 やっぱり。 |
| しないでしょうね。 |
|
| 生姜で食べるイメージがありますよね。 |
|
| わたしは寿司ですね。 にぎりで。 |
|
| 今ふと思ったんですけど 刺身で山葵で食べるのと 生姜で食べるのの違いって 何か規則があるんですかね。 烏賊とか鰹は生姜ですよね。 鰺も生姜で食べますよね。 |
|
| 薬味ねえ。 |
|
| ── | なまぐさ系が生姜。 鯛は山葵ですし。 |
| 山葵ですよね。 |
|
| ── | 間八も山葵ですね。 |
| しめ鯖とか、しめたものはどうですか。 |
|
| しめ鯖は山葵ですね。 |
|
| ── | 脂が多い? あ、でも鮪は山葵ですね。 生姜と山葵の使い分けがわかりません。 鰹だと大蒜でという人も。 |
| 大蒜か生姜っていうのがありますね。 |
|
| ── | 鰹は虫がいるから殺菌ですよね。 |
| ああ、そっかそっか。 |
|
| ── | 虫がいるっていわれるものは 生姜ですかね。 烏賊もそうですよね。 |
| でも山葵も殺菌効果ありますよね。 |
|
| ── | あります、ね(笑)。 |
| 前の候を ひっぱるわけじゃないですけど、 茗荷を薬味にして刺身を食べても おいしいんじゃないですか。 |
|
| 絶対おいしいと思います。 |
|
| ── | シャクシャク感があるので サラダっぽい感じに。 |
| 魚の肉を純粋に味わうには ちょっと邪魔する感じなんですかね。 |
|
| なるほどねえ。 |
|
| ── | 最近、刺身を食うのに ちょっといたずらをしまして。 「燻製しょうゆ」と 「燻製オリーブオイル」 っていうのをもらったんですよ。 それをかけたらですね、 うまいのなんの。 なんにでも合う。 |
| ブレンドするんですか? |
|
| ── | 両方かけちゃうんです。 |
| 調味料って、一旦ハマると しばらくブームが続きますよね。 飽きるまで。 |
|
| 白身ですか、やっぱり。 |
|
| ── | もう全部やっちゃいます。 鮪でも合いました。 |
| んん~ん! おいしそう。 |
|
| ── | 調べてみました。 山葵と生姜の使い分けは、 「ベターホームのお料理教室」 というところにございましたが、 山葵は辛さに持続性がなく、 タイやヒラメなど淡泊な味の魚に向いていると。 一方生姜は刺激もありますが、 生臭みの成分と結びついて、 臭い自体を消そうとする働きがあるとのことです。 だからくせの強い魚に添えられる。 臭い自体を消す働きが あるかないかということですね。 生姜はアロマがありますからね。 |
| 勉強になりました! |
|
| ── | ということで季節のくだものは「枇杷」です。 枇杷はいいですねえ~。 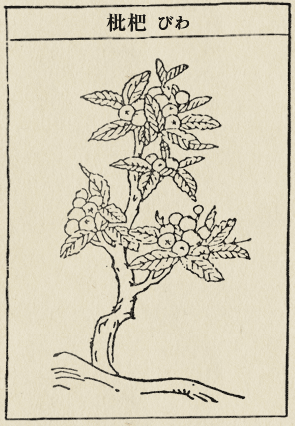 |
| しかも枇杷って短い期間しか ないんですよね。 すぐ茶色くなって傷むし。 |
|
| ── | ほんとに旬の時にしか食べられないから 貴重さがありますね。 |
| 千葉に行くと 「枇杷羊羹」とか 枇杷のお菓子が名産ですよね。 |
|
| 千葉ってそんな枇杷が盛んなんですか。 |
|
| 房総半島で。 |
|
| ── | そして、お庭のあるうちでは 実がなってますよね。 |
| はい。街路樹もありますね。 |
|
| ── | たわわに実ってますね。 |
| 漢方のイメージもありますよね。 |
|
| ── | 枇杷の葉。お茶にしたり、 煎じ薬は湿布になったり。 |
| 不思議に品種にバリエーションを見ないですよね。 枇杷のいろんな色があったり いろんな大きさがあったりしない。 |
|
| ── | そうですね、交配種とか見ないですよね。 |
| そうそう。 もっと肉厚になってくれると いいなといつも思うんですけど。 |
|
| ── | そうそう! 桃くらい大きくなってくれても 食べるのに。 |
| ねえ! 種大きいんだもん。 |
|
| 原産ってどこなんですかねえ。 アジアですか。 |
|
| ── | 中国南西部だそうです。 中国からインド、ハワイ、 日本からはイスラエル、 ブラジルに広がったそうですよ。 「トルコ、レバノン、ギリシャ、 イタリア南部、 スペイン、フランス南部、 アフリカ北部でも栽培されている」と。 |
| え、あるんですか、そんな! |
|
| ── | けっこうワールドワイドですね。 この淡泊な味が受け入れられるのかな? でも果実酒にしたり、ジャムにしたり コンポートにしたりもできますからね。 ということで、今回もありがとうございました。 次回は「梅子黄(うめの み きばむ)」。 6月15日にお会いしましょう。 |
| 2013-06-10-MON |