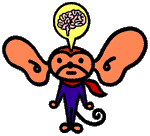 |
| 海馬。 頭は、もっといい感じで使える。 |
|
第2回 生きることに慣れてはいけない 今日は、まずはじめに、ほんまもんのニュースから。 あなたは、5月2日の新聞を、読みましたか? http://www.yomiuri.co.jp/top/20020502it01.htm ↑こちらは「読売新聞」にリンクをはりましたが、 もうすぐ『海馬』を出版する池谷裕二さんの研究室が、 アルツハイマー病の発症のメカニズムを つきとめた、という報道があったのですよ。  記事の中で池谷さんは、 「βアミロイドがグリア細胞に作用する仕組みを さらに詳しく調べ、新薬開発につなげたい」 という渋いコメントを述べる人として登場しています。 アルツハイマー病のための新薬開発は、 記憶を研究テーマにしている池谷さんにとっては、 ひとつの大きな目標だと、「ほぼ日」も伺っておりました。 だからこそ、脳の記憶について、長期記憶の入口である 「海馬」という部位から研究している・・・と、 これは今度の単行本の中でも語られることなのです。 今日は、脳についての話題の端緒として、まずは、 池谷さんが単行本の冒頭で話している部分を、紹介します。 ここで話してくれた内容は、今後わたしたちが 脳や海馬や生き方についてを探ってゆく旅の、 最初の方位磁針のような役目を果たすと思います。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 【※池谷裕二さんによる談話】 「最近もの忘れがひどい」という話をよく聞きます。 「もうこの年齢だから、脳を鍛えるといっても限りがある」 という声もよく聞きます。 だけど、ほんとうはそんなことはないんです。 その誤解を解くだけでも、 ずいぶん違うのではないかなぁと思っています。 例えば、ぼくは、まわりの人があきれてしまうぐらいに、 もの忘れをしてしまいます。 学生に「こういう実験をしたら?」と言ったはずなのに、 一週間後にその実験をしている姿を見て 「なんでそういう実験をやっているの?」 と訊いたりする。挙句の果てに、 「その実験はあまり意味がない」 みたいなことさえも言ってしまう・・・。 もの忘れがひどいのは昔からなのです。  だけどぼくは、忘れっぽくても 「もっと覚えたいなぁ」「年をとったから忘れっぽくて」 というようには、あまり思いません。 痴呆のような病気をのぞけば、 「年を取ったからもの忘れをする」 というのは、科学的には間違いなんです。 痴呆の症状としてのもの忘れは、 ふつうに言われる「忘れっぽい」ということとは、 明らかに一線を画すものですし。 もの忘れやド忘れが増えると思えてしまう理由は、 いくつかあります。 子どもの頃に比べておとなは たくさんの知識を頭の中に詰めているから、 そのたくさんの中から知識を選び出すのに時間がかかる。 「おとなが一万個の知識の中から ひとつを選ぶようなものとしたら、 子どもは十個の記憶の中から ひとつ選びだすだけだからすぐにできる」 というような比喩ができます。 ただ、それだけのことなのです。 生きてきた上でたくさんの知識を蓄えたわけだから、 これはもう仕方のないことと言っていいと思います。 それと実は、子どももたくさんド忘れをするんです。  ぼくも小さい頃から あちこちにものを置き忘れて困った記憶があるのですが、 ただ、子どもはそのド忘れを気にしていないだけ。 それが健全な姿だと思います。 おとなと子どもとでは、記憶の種類が変わるだけなんですよ。 おとなと子どもとの違いとして、もっとも大きな点は、 「子どもはまわりの世界に白紙のまま接するから、 世界が輝いて見えている。 何に対しても慣れていないので、 まわりの世界に対して興味を示すし、世界を知りたがる。 だけど、おとなになると マンネリ化したような気になって、 これは前に見たものだなと整理してしまう」 ということになるのだと思います。 おとなはマンネリ化した気になってモノを見ているから、 驚きや刺激が減ってしまう。 刺激が減るから、印象に残らずに 記憶力が落ちるような主観を抱くようになる・・・・・・。  ですから、脳の機能が低下しているかどうか、 ということよりも、 まわりの世界を新鮮に見ていられるかどうか ということのほうを、ずっと気にしたほうがよいでしょう。 生きることに慣れてはいけないんです。 慣れた瞬間から、 まわりの世界はつまらないものに見えてしまう。 慣れていない子どものような視点で世界を見ていれば、 おとなの脳は想像以上に潜在能力を発揮するんですよ。 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ (※次回はあさって木曜におとどけ。おたのしみに!) |
2002-05-07-TUE
 戻る |